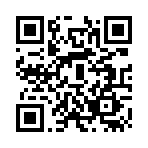2014年11月26日
はりはら塾 10月
10月の講座のご紹介を遅ればせながら・・・。

第7回講座のご案内
神無月、日本中の神々が出雲に出張しています。神様たちは出雲大社の上宮(かみのみや)で神議(かみはか)りという寄り合いをするそうな。主な議題は、人と人の縁・人の生死、寿命・来年の天候・米や酒の出来などだそうです。
この間にお留守番をしてくださるのが、一般家庭では台所の大黒様、商家では恵比寿様。恵比寿講は神様の仲間がいない事を慰める意味もあるんだとか・・。日本はやっぱり神様が創った国なんですね。。。
小習いコース
月にも不思議なパワーがあるといわれます。「十三夜」は栗名月、先月の十五夜にも劣らぬ人気で、まん丸ではない不十分さに趣を感じますがいかがでしょうか。
山の空気もひんやりと、紅葉には少々早いですが、ご近所のキンモクセイのオレンジがかった黄色の花と芳香が嬉しい季節です。
「蒸しパン」
蒸しパン(むしパン)は、菓子の一種。小麦粉に重曹やベーキングパウダー、砂糖等を混ぜ、捏ねてから成形し、蒸し器で蒸したもの。特に果物などをのせたものは蒸しケーキとも呼ばれます。
明治期に膨張剤としての重曹の入手が手軽になり、醗酵の手間が省かれ、蒸籠で作ることができる蒸しパンは、子どものおやつや米にかわる代用食としても食されるようになります。大正時代の米騒動の頃に玄米パンと呼ばれる玄米の蒸しパンが誕生。見た目は餡を抜いた饅頭のようなもので、あまり美味しいとはいえず、当時の不景気を象徴するものだったようです。戦後は砂糖が貴重だったため、さつまいもや栗を混ぜておやつとしても食されていました。懐かしくは、ロバ(実際には木曽馬を使用)に荷車を引かせて販売していたロバのパン屋が一世を風靡した記憶も。。。
コンビニの普及で、日持ちのしない蒸しパンも流通経路に載せられるようになり、大手製パン業者も蒸しパンを製造販売するようになり、黒糖・ヨモギ・サツマイモなどの伝統的な風味のもののほか、チーズ、チョコレート、マンゴーなどの新しい風味のバラエティーも豊富です。また米粉のパン類への利用が増えるようになる中、米粉を加えたもちもちとした食感の蒸しパンも作られています。また、ホットケーキミックスを代用にして、蒸す代わりに電子レンジで過熱する手軽に作る方法が考案され一段と手軽さが増しました。
蒸しパンは甘くやわらかく消化吸収がよいため幼児のおやつにも合います。その際は野菜を練りこむと幼児に不足しがちなビタミン類の摂取に役立ち、母親の味としてより記憶に残りやすいんだとか。。。

本コース
野山は秋の七草がそろい、季節の変化が実感出来ます。春の七草は食べて無病息災を願う中国伝来の習慣ですが、こちらは日本人の感性が作った「趣」を味わうもののようです。川柳にも「秋の七草、春よりも野暮でなし」とあります。
「山 路(仮称) 浮島と羊羹の流し合わせ」
初夏に独特の匂いを漂わせた栗の花も、秋が進むにつれて実を結び毬栗が大きくなっていきます。青い毬に包まれた「若栗」、実が熟して「笑栗」、梢から落ちて「落栗」、そんな秋の味覚で美味しいお菓子を頂きたいものです。。今回は茶席菓子としても饗される「浮島」、名前からもふわふわ感が伝わってきます。餡を主体にした蒸しかすてらなので、口どけもよく、卵の気泡で浮かせた生地は香りも豊かです。
紅葉は気温が急激に下がる事で葉っぱの中のたんぱく質が移動できなくなり、糖類が蓄積されて、緑の色素が減っていくために起こる現象です。代わりに増えていく赤い色素はアントシアニン、黄入り色素はカロチノイド、褐色の色素はフロパフェン。木によって、気候によって、どの色が強く見えるのかは異なるそうです。一様に赤くならないからこそ、色のグラデーションが楽しめて秋を目で「狩る」ことができるんでしょう。
山路を散策しながらの紅葉狩りをイメージして、着色や配色を工夫して、秋を司る女神「龍田姫」になった気分で、温かいティータイムはいかがでしょうか。。。。」



第7回講座のご案内
神無月、日本中の神々が出雲に出張しています。神様たちは出雲大社の上宮(かみのみや)で神議(かみはか)りという寄り合いをするそうな。主な議題は、人と人の縁・人の生死、寿命・来年の天候・米や酒の出来などだそうです。
この間にお留守番をしてくださるのが、一般家庭では台所の大黒様、商家では恵比寿様。恵比寿講は神様の仲間がいない事を慰める意味もあるんだとか・・。日本はやっぱり神様が創った国なんですね。。。
小習いコース
月にも不思議なパワーがあるといわれます。「十三夜」は栗名月、先月の十五夜にも劣らぬ人気で、まん丸ではない不十分さに趣を感じますがいかがでしょうか。
山の空気もひんやりと、紅葉には少々早いですが、ご近所のキンモクセイのオレンジがかった黄色の花と芳香が嬉しい季節です。
「蒸しパン」
蒸しパン(むしパン)は、菓子の一種。小麦粉に重曹やベーキングパウダー、砂糖等を混ぜ、捏ねてから成形し、蒸し器で蒸したもの。特に果物などをのせたものは蒸しケーキとも呼ばれます。
明治期に膨張剤としての重曹の入手が手軽になり、醗酵の手間が省かれ、蒸籠で作ることができる蒸しパンは、子どものおやつや米にかわる代用食としても食されるようになります。大正時代の米騒動の頃に玄米パンと呼ばれる玄米の蒸しパンが誕生。見た目は餡を抜いた饅頭のようなもので、あまり美味しいとはいえず、当時の不景気を象徴するものだったようです。戦後は砂糖が貴重だったため、さつまいもや栗を混ぜておやつとしても食されていました。懐かしくは、ロバ(実際には木曽馬を使用)に荷車を引かせて販売していたロバのパン屋が一世を風靡した記憶も。。。
コンビニの普及で、日持ちのしない蒸しパンも流通経路に載せられるようになり、大手製パン業者も蒸しパンを製造販売するようになり、黒糖・ヨモギ・サツマイモなどの伝統的な風味のもののほか、チーズ、チョコレート、マンゴーなどの新しい風味のバラエティーも豊富です。また米粉のパン類への利用が増えるようになる中、米粉を加えたもちもちとした食感の蒸しパンも作られています。また、ホットケーキミックスを代用にして、蒸す代わりに電子レンジで過熱する手軽に作る方法が考案され一段と手軽さが増しました。
蒸しパンは甘くやわらかく消化吸収がよいため幼児のおやつにも合います。その際は野菜を練りこむと幼児に不足しがちなビタミン類の摂取に役立ち、母親の味としてより記憶に残りやすいんだとか。。。

本コース
野山は秋の七草がそろい、季節の変化が実感出来ます。春の七草は食べて無病息災を願う中国伝来の習慣ですが、こちらは日本人の感性が作った「趣」を味わうもののようです。川柳にも「秋の七草、春よりも野暮でなし」とあります。
「山 路(仮称) 浮島と羊羹の流し合わせ」
初夏に独特の匂いを漂わせた栗の花も、秋が進むにつれて実を結び毬栗が大きくなっていきます。青い毬に包まれた「若栗」、実が熟して「笑栗」、梢から落ちて「落栗」、そんな秋の味覚で美味しいお菓子を頂きたいものです。。今回は茶席菓子としても饗される「浮島」、名前からもふわふわ感が伝わってきます。餡を主体にした蒸しかすてらなので、口どけもよく、卵の気泡で浮かせた生地は香りも豊かです。
紅葉は気温が急激に下がる事で葉っぱの中のたんぱく質が移動できなくなり、糖類が蓄積されて、緑の色素が減っていくために起こる現象です。代わりに増えていく赤い色素はアントシアニン、黄入り色素はカロチノイド、褐色の色素はフロパフェン。木によって、気候によって、どの色が強く見えるのかは異なるそうです。一様に赤くならないからこそ、色のグラデーションが楽しめて秋を目で「狩る」ことができるんでしょう。
山路を散策しながらの紅葉狩りをイメージして、着色や配色を工夫して、秋を司る女神「龍田姫」になった気分で、温かいティータイムはいかがでしょうか。。。。」

2014年11月25日
牧之原市産業祭2014
牧之原市産業祭2014
お天気もポカポカでたくさんのお客様のご来場でした。

自前のテントで出店、

特製小豆皮むき餡と新小豆のお汁粉と焼き立てのミニどら焼きの試食を提供


今回初登場の手書きのA看板、

「ゆず茶ま~ぶる」は、ふじのくに食の都づくり仕事人ウィーク冬至祭の参加商品
ミニパウンドケーキに柚子の香りとやぶきた茶を加えてマーブル模様に仕上げました。
期間を前に先行発売です。
お天気もポカポカでたくさんのお客様のご来場でした。

自前のテントで出店、

特製小豆皮むき餡と新小豆のお汁粉と焼き立てのミニどら焼きの試食を提供


今回初登場の手書きのA看板、

「ゆず茶ま~ぶる」は、ふじのくに食の都づくり仕事人ウィーク冬至祭の参加商品
ミニパウンドケーキに柚子の香りとやぶきた茶を加えてマーブル模様に仕上げました。
期間を前に先行発売です。


 ふるさと創菓処 扇松堂
ふるさと創菓処 扇松堂
 住所
住所 電話・FAX
電話・FAX 営業時間
営業時間 定休日
定休日  駐車場
駐車場 アクセス
アクセス