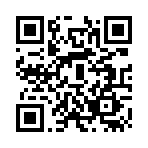2012年08月21日
若栗
暦では秋が立って暫くしますが、まだまだ残暑厳しいです。
でも、里山では秋の気配が感じられます。
初秋の里の味覚「栗」
まだ青いですがイガイガは立派な栗の風体です。
初秋の雰囲気を感じていただければ・・・・。
外郎生地に栗餡を包み、氷餅を細かくして付け、少しひねって「青い栗のイガ」を表してみました。


でも、里山では秋の気配が感じられます。
初秋の里の味覚「栗」
まだ青いですがイガイガは立派な栗の風体です。
初秋の雰囲気を感じていただければ・・・・。
外郎生地に栗餡を包み、氷餅を細かくして付け、少しひねって「青い栗のイガ」を表してみました。

2012年08月21日
はりはら塾「葛焼き」
はりはら塾「いと、お菓子!」講座 第5回講座です。
「葛焼き」
葛桜や水饅頭に代表される「葛菓子」は、生地に透明感があり、見るからに涼しげで、よく冷やしてひんやりつるんとした口あたりを楽しむ夏の菓子です。
「葛」はもともと薬餌として用いられるなど、古くから日本人の食生活に関わりの深い食材で、根からは葛澱粉(クズコ:葛粉)が採れます。この根はカッコン(葛根)と呼ばれ,漢方薬として使われます(葛根湯など)。菓子の材料に取り入れられるようになったのは鎌倉~室町の時代からといわれます。「葛粉」を得るために、葛の根から澱粉を精製するのはとても手間のかかる作業であり、当然生産量も限られ、純正品はとても高価です。よって、葛粉と称しながらも馬鈴薯澱粉などを混ぜ入れた廉価なものが多いのも事実です。生地にした時の滑らかさや透明感、口あたりなどは上質なものほど優れています。
現代では、河川の土手や里地を覆い、厄介な雑草の代表格とも言われるクズですが、秋の七草にも数えられ、山上憶良も万葉集で「萩の花 尾花葛花 なでしこが花 をみなへし また藤袴 朝顔が花」と 詠んでいます。蔓は強靭で,葛布を作るときの材料とされます。
葛を焼くのは関西の発想で、関東ではほとんど見かけません。片栗粉の手粉で粒餡を包んで、表面にうっすらと焼き目をつけての仕上げです。

手前が栗餡、奥が粒餡を包んであります。
「葛焼き」
葛桜や水饅頭に代表される「葛菓子」は、生地に透明感があり、見るからに涼しげで、よく冷やしてひんやりつるんとした口あたりを楽しむ夏の菓子です。
「葛」はもともと薬餌として用いられるなど、古くから日本人の食生活に関わりの深い食材で、根からは葛澱粉(クズコ:葛粉)が採れます。この根はカッコン(葛根)と呼ばれ,漢方薬として使われます(葛根湯など)。菓子の材料に取り入れられるようになったのは鎌倉~室町の時代からといわれます。「葛粉」を得るために、葛の根から澱粉を精製するのはとても手間のかかる作業であり、当然生産量も限られ、純正品はとても高価です。よって、葛粉と称しながらも馬鈴薯澱粉などを混ぜ入れた廉価なものが多いのも事実です。生地にした時の滑らかさや透明感、口あたりなどは上質なものほど優れています。
現代では、河川の土手や里地を覆い、厄介な雑草の代表格とも言われるクズですが、秋の七草にも数えられ、山上憶良も万葉集で「萩の花 尾花葛花 なでしこが花 をみなへし また藤袴 朝顔が花」と 詠んでいます。蔓は強靭で,葛布を作るときの材料とされます。
葛を焼くのは関西の発想で、関東ではほとんど見かけません。片栗粉の手粉で粒餡を包んで、表面にうっすらと焼き目をつけての仕上げです。

手前が栗餡、奥が粒餡を包んであります。
2012年08月20日
夏休み
夏休みの榛原中学校、ソフトテニス部にお邪魔してかき氷してきました。

こんなもので大喜び頂いて・・・、恐縮です。
自家製の蜜持参、生果汁入りの特製です。

富士常葉大学 山田辰巳教授が理事長を務めるNPO法人里の楽校のキャンプでも好評頂いたみたいで・・・
次、
名前はゴキブリですが、台所や食堂などで見かける例のすばしっこい残飯漁りの嫌われゴキブリとは、その行動は全く違います。
食べ物も、カブトムシやクワガタムシたちのように、朽ちた木をを食べて生きています。
ですから、森林の掃除屋であっても、決して汚い虫ではないのです。
ゴキブリの仲間は、生活力があり、数億年前から、その姿を大きく変えることなく生きて来たと言われます。
私たちヒトとは、その歴史が全く違うのです。先輩も先輩、大先輩なのです。
台所などを動き回るゴキブリでなく、オオゴキブリの場合は、いじめないで見守ってあげたいと思います。
写真は、榛原総合運動公園のテニスコートでゲットのオオゴキブリです。

オオゴキブリの羽の先端は、磨り減って欠けていることが多いらしいのですが
これはしっかりと残っているようです。
次、珍客。。。
先日、自宅倉庫の前にてゲット!!!
ヤマカガシです。
一部がオレンジ色の綺麗なヘビですが、毒の持ち主です。。。

次、強制的に来客。。。
勝間田川にてゲット!!!
夏バテには最高の食材、ウナギ
今年は3匹目、でもすべて鉛筆サイズでして、前出スッポンのぽんちゃんにあげました。


こんなもので大喜び頂いて・・・、恐縮です。
自家製の蜜持参、生果汁入りの特製です。

富士常葉大学 山田辰巳教授が理事長を務めるNPO法人里の楽校のキャンプでも好評頂いたみたいで・・・

次、
名前はゴキブリですが、台所や食堂などで見かける例のすばしっこい残飯漁りの嫌われゴキブリとは、その行動は全く違います。
食べ物も、カブトムシやクワガタムシたちのように、朽ちた木をを食べて生きています。
ですから、森林の掃除屋であっても、決して汚い虫ではないのです。
ゴキブリの仲間は、生活力があり、数億年前から、その姿を大きく変えることなく生きて来たと言われます。
私たちヒトとは、その歴史が全く違うのです。先輩も先輩、大先輩なのです。
台所などを動き回るゴキブリでなく、オオゴキブリの場合は、いじめないで見守ってあげたいと思います。
写真は、榛原総合運動公園のテニスコートでゲットのオオゴキブリです。

オオゴキブリの羽の先端は、磨り減って欠けていることが多いらしいのですが
これはしっかりと残っているようです。
次、珍客。。。
先日、自宅倉庫の前にてゲット!!!
ヤマカガシです。
一部がオレンジ色の綺麗なヘビですが、毒の持ち主です。。。

次、強制的に来客。。。
勝間田川にてゲット!!!
夏バテには最高の食材、ウナギ
今年は3匹目、でもすべて鉛筆サイズでして、前出スッポンのぽんちゃんにあげました。

2012年08月16日
はりはら塾「角きんつば」
はりはら塾 いと、お菓子!小習いコース 第5回の講座
角きんつばを作りました。
素朴さで、変わらぬ人気の和菓子のひとつ「角きんつば」は皮種に包まれた小豆が身上のあんこの餅菓子、そもそもは西の「銀つば」が前身の『下り菓子』です。江戸時代に京の都でうるち米粉の皮で小豆の餡を包んで焼いた焼き餅が人気となりまして、楕円形に成形し表面に指で押した形態が刀のつばに似ている事から「銀つば」と呼ばれ、これが江戸に伝わり「金つば」と改名され、皮も小麦粉を薄くひいて小粋にしたてるようになったと。。。。そして幕末には四角のものが人気となり今日まで至っています。
北海道小豆のアクを丁寧に除きながら軟らかく煮あげて、砂糖を加え寒天で固めた小倉羊羹を、お好みのサイズに切り分けて、周りを水種で一面ずつ丁寧にくるむように、白い網目模様に焼きあげれば出来上がり。。。。。羊羹の甘さが、なぜかサッパリ味に感じます。
出来たてを冷茶で頂くのもいいですが、少し冷えて餡と皮が馴染んだころに渋い煎茶でいただくと、小豆の旨さが際立つように思います。。。

小倉羊羹の面に水種をつけて、丁寧に一面づつ仕上げます。

冷めて生地が馴染んだ頃が食べごろ・・・。
今回は栗の甘露煮を加えて少しだけ贅沢に。。。
見た目以上にさっぱりとした食べ口だと思います。
角きんつばを作りました。
素朴さで、変わらぬ人気の和菓子のひとつ「角きんつば」は皮種に包まれた小豆が身上のあんこの餅菓子、そもそもは西の「銀つば」が前身の『下り菓子』です。江戸時代に京の都でうるち米粉の皮で小豆の餡を包んで焼いた焼き餅が人気となりまして、楕円形に成形し表面に指で押した形態が刀のつばに似ている事から「銀つば」と呼ばれ、これが江戸に伝わり「金つば」と改名され、皮も小麦粉を薄くひいて小粋にしたてるようになったと。。。。そして幕末には四角のものが人気となり今日まで至っています。
北海道小豆のアクを丁寧に除きながら軟らかく煮あげて、砂糖を加え寒天で固めた小倉羊羹を、お好みのサイズに切り分けて、周りを水種で一面ずつ丁寧にくるむように、白い網目模様に焼きあげれば出来上がり。。。。。羊羹の甘さが、なぜかサッパリ味に感じます。
出来たてを冷茶で頂くのもいいですが、少し冷えて餡と皮が馴染んだころに渋い煎茶でいただくと、小豆の旨さが際立つように思います。。。

小倉羊羹の面に水種をつけて、丁寧に一面づつ仕上げます。

冷めて生地が馴染んだ頃が食べごろ・・・。
今回は栗の甘露煮を加えて少しだけ贅沢に。。。
見た目以上にさっぱりとした食べ口だと思います。
2012年08月16日
秋立ちましたが・・・
暦の上では秋が立ち
お盆も過ぎて涼しい風が・・・・・・・、まだまだです。
季節を先取りではありませんが、秋の七草のひとつ
山上憶良も万葉集で「萩の花 尾花葛花 なでしこが花 をみなへし また藤袴 朝顔が花」と 詠んでいます。
この朝顔が「桔梗」です。

練りきり 小豆漉し餡 製
お盆も過ぎて涼しい風が・・・・・・・、まだまだです。
季節を先取りではありませんが、秋の七草のひとつ
山上憶良も万葉集で「萩の花 尾花葛花 なでしこが花 をみなへし また藤袴 朝顔が花」と 詠んでいます。
この朝顔が「桔梗」です。

練りきり 小豆漉し餡 製


 ふるさと創菓処 扇松堂
ふるさと創菓処 扇松堂
 住所
住所 電話・FAX
電話・FAX 営業時間
営業時間 定休日
定休日  駐車場
駐車場 アクセス
アクセス