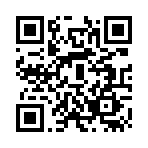2019年04月22日
2019 いと、お菓子! 始まりました
開講・初回講座のご案内
「世の中に 絶えて桜のなかりせば 春の心はのどけからまし」(世の中に桜というものが無かったなら、さぞのどかに春を過ごせるだろうになあ)伊勢物語の主人公とされる在原業平の句です。日本列島では桜前線が北上し、南から桜が咲きほころび始めています。桜の開花は春のセンサーとして日本全土を縦断します。「花疲れ」「花盗人」「花の雨」花とは桜を指します。見るも良し、味わうも美味し、詠むも愉しい桜の季節が巡ってきます。一年間、宜しくお願いいたします。
県営吉田公園緑化大学「いと、お菓子!」
お題「卯月」
菓子銘「ひとひら・サクラ」

はりはら塾「いと、お菓子!」
三色団子風桜餅
桜餅には、「道明寺」と「長命寺」の2種類があります。一般的に、「道明寺」は、関西風・上方風の桜餅。「長命寺」は、関東風・江戸風の桜餅。
関西風の桜餅は「道明寺粉」という材料を使用します。道明寺粉とは、もち米を一度蒸して、乾燥させて粗く砕いた物。これを蒸して色付けしたもので餡を包んで作ります。お米の食感が残るつぶつぶとした皮が特徴です。道明寺粉の歴史は古く、戦国時代に大阪の道明寺というお寺で作っていた保存食「干飯(ほしい)」が元になっています。干飯を挽いて粉にしたものを「道明寺粉」、それを使った餅が道明寺と呼ばれるようになったそうです。
関東風と言われている「長命寺」。皮の材料には小麦粉が使われています。江戸時代、東京の隅田川沿いにある長命寺の門番、山本新六が桜の葉を集めて塩漬けにし、餅をくるんで花見の席で売り出したのが始まりと言われます。
共通しているのが、餅を包んでいる「塩漬けの桜の葉」の存在。桜の葉で包むことで、香り付けやお餅の乾燥を防ぐ目的があるんだとか。葉は食べる人と食べない人で意見が分かれるようですが、正式な食べ方は決まっていません。お好みでどうぞ!
今回は、見かけは三色団子ですが、道明寺粉を使った正真正銘桜餅。桜餅の中は、こしあん、白あん、桜あんの3色構造。1本で3つの味が楽しめます。

「世の中に 絶えて桜のなかりせば 春の心はのどけからまし」(世の中に桜というものが無かったなら、さぞのどかに春を過ごせるだろうになあ)伊勢物語の主人公とされる在原業平の句です。日本列島では桜前線が北上し、南から桜が咲きほころび始めています。桜の開花は春のセンサーとして日本全土を縦断します。「花疲れ」「花盗人」「花の雨」花とは桜を指します。見るも良し、味わうも美味し、詠むも愉しい桜の季節が巡ってきます。一年間、宜しくお願いいたします。
県営吉田公園緑化大学「いと、お菓子!」
お題「卯月」
菓子銘「ひとひら・サクラ」

はりはら塾「いと、お菓子!」
三色団子風桜餅
桜餅には、「道明寺」と「長命寺」の2種類があります。一般的に、「道明寺」は、関西風・上方風の桜餅。「長命寺」は、関東風・江戸風の桜餅。
関西風の桜餅は「道明寺粉」という材料を使用します。道明寺粉とは、もち米を一度蒸して、乾燥させて粗く砕いた物。これを蒸して色付けしたもので餡を包んで作ります。お米の食感が残るつぶつぶとした皮が特徴です。道明寺粉の歴史は古く、戦国時代に大阪の道明寺というお寺で作っていた保存食「干飯(ほしい)」が元になっています。干飯を挽いて粉にしたものを「道明寺粉」、それを使った餅が道明寺と呼ばれるようになったそうです。
関東風と言われている「長命寺」。皮の材料には小麦粉が使われています。江戸時代、東京の隅田川沿いにある長命寺の門番、山本新六が桜の葉を集めて塩漬けにし、餅をくるんで花見の席で売り出したのが始まりと言われます。
共通しているのが、餅を包んでいる「塩漬けの桜の葉」の存在。桜の葉で包むことで、香り付けやお餅の乾燥を防ぐ目的があるんだとか。葉は食べる人と食べない人で意見が分かれるようですが、正式な食べ方は決まっていません。お好みでどうぞ!
今回は、見かけは三色団子ですが、道明寺粉を使った正真正銘桜餅。桜餅の中は、こしあん、白あん、桜あんの3色構造。1本で3つの味が楽しめます。



 ふるさと創菓処 扇松堂
ふるさと創菓処 扇松堂
 住所
住所 電話・FAX
電話・FAX 営業時間
営業時間 定休日
定休日  駐車場
駐車場 アクセス
アクセス