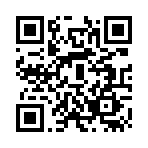2016年04月25日
再開。。。いと、お菓子!
2016 扇松堂の「いと、お菓子!」 再開
はりはら塾のご案内
開講・初回講座のご案内
春分。冬至から畳の目一目ずつ日が伸びて、夕暮れが暮れそうでなかなか暮れない様子を「暮れなずむ」。この季節に聴くアノ曲の冒頭にも歌われます。春の錦、芳春、花曇り、春愁、春雷、花散らし、春爛漫の季節を表す言葉からも、先人の萌いずる春を謳歌する気持ちは尽きなかったようです。月に朧がかかる春の夜を「春宵一刻値千金」、お楽しみください。
はりはら塾「いと、お菓子!」にご参加いただき有難う御座います。一年間、宜しくお願いいたします。
下記の通り、開講と初回の講座をご案内いたします。
小習いコース
江戸名物「長命寺さくら餅」
桜は今や日本人だけでなく、世界中の人に愛されています。しかしながら、花や葉を食材として利用することによって、その風味や香りを楽しむのは日本人だけのようです。
1717年に江戸の長命寺の門番、山本新六が桜の葉を集めて塩漬けにし、餅をくるんで花見の席で売り出したのが始まりと言われる「長命寺さくら餅」・・・。作り方は至ってシンプル。作りたてのモチモチ感が最高に美味しいと思います。関西風の道明寺桜餅との違いもウンチクのひとつに加えてください・・・・・(*^_^*)。

本コース
葉桜餅 (もち米製)
葉桜(はざくら)とは、桜の花が散り若葉が出始めた頃から新緑で覆われた時期までの桜の木、またはその様を言い、俳句の世界では、夏の季語として用いられます。
花びらが散り始め、同時に若葉が芽吹き始めて新緑の葉の色が混ざり、遠目にくすんで見える頃から、桜の花びらが全て落花し、めしべ・おしべが残って樹木全体に赤みが残っている頃まで、あるいは、樹木全体が新緑の葉で瑞々しく艶を帯びた状態で覆われる頃までです。それ以降の時期で単に葉が茂っている状態の桜を葉桜と呼ぶことはありません。桜の開花状態を示す指標の一分咲き・二分咲きと同様に葉桜では葉と花の割合を示す言葉として満開以降は舞い始め、六分葉桜、七分葉桜、八分葉桜、九分葉桜のように呼ばれます。ん~、いささか難しい(―_―)!!

おまけ。。。
桜の葉の塩漬けについて
木の樽に平たく重ねて入れた桜の葉は塩漬けされ、さくら葉(さくらば)と呼ばれ食用として利用されます。さくら葉はほのかな香りを活かし、桜餅やアイスクリーム、クッキーなどに混ぜ、香り付けの材料として用いられ、好評です。春の桜餅を包む食用のさくら葉は大島桜の葉を用い、静岡県賀茂郡松崎町が日本一の生産量で全国需要の7割を占めています。さくら葉の香りの成分は芳香属化合物のクマリンと呼ばれる精油成分に由来するもので生の葉ではあまり匂いませんが、塩漬けされることで香りが現れます。食用に大島桜が用いられる理由は他の桜に比べてクマリンが多いことによりますが、1876年には人工的にも合成されたそうです。
JAハイナン相良の女性部にて
味噌饅頭
ご存じのとおり、味噌(一部地域は、黒糖)を用いた饅頭です。一般的には「みそまん」と呼ばれ日本全域にあり、地方の銘菓や土産菓子として、定番のおやつとして多くの甘党を魅了しています。餡の甘みと味噌の辛味が合って人気で、どなたも一度はお召し上がりの経験はあろうかと思います。
味噌を生地に入れるタイプ、餡に入れるタイプ、饅頭の色だけが味噌に似ているだけのタイプなどがあり、味・香り・色で味噌の風味を演出します。使用される味噌は色々で、土産菓子などには、製造される地域の特産のものが使われていることが多いです。食感も多様で、薄皮タイプ・ふんわりタイプ・ザラメ糖などを使用する配合もあり、菓子の銘は同じでも、各店では全く違った製品となっていて、これほどに作り手の好みやこだわりが反映される菓子は珍しいかもしれません。

中国からのお客様が日本の伝統文化を遊学の旅
「旧木下邸・勝間田塾にて和菓子作り体験」

旧木下邸

鴬・桜


県営吉田公園緑花大学
お題「さくら」

花筏・桜花 練りきり 小豆漉し餡、桜餡 製
はりはら塾のご案内
開講・初回講座のご案内
春分。冬至から畳の目一目ずつ日が伸びて、夕暮れが暮れそうでなかなか暮れない様子を「暮れなずむ」。この季節に聴くアノ曲の冒頭にも歌われます。春の錦、芳春、花曇り、春愁、春雷、花散らし、春爛漫の季節を表す言葉からも、先人の萌いずる春を謳歌する気持ちは尽きなかったようです。月に朧がかかる春の夜を「春宵一刻値千金」、お楽しみください。
はりはら塾「いと、お菓子!」にご参加いただき有難う御座います。一年間、宜しくお願いいたします。
下記の通り、開講と初回の講座をご案内いたします。
小習いコース
江戸名物「長命寺さくら餅」
桜は今や日本人だけでなく、世界中の人に愛されています。しかしながら、花や葉を食材として利用することによって、その風味や香りを楽しむのは日本人だけのようです。
1717年に江戸の長命寺の門番、山本新六が桜の葉を集めて塩漬けにし、餅をくるんで花見の席で売り出したのが始まりと言われる「長命寺さくら餅」・・・。作り方は至ってシンプル。作りたてのモチモチ感が最高に美味しいと思います。関西風の道明寺桜餅との違いもウンチクのひとつに加えてください・・・・・(*^_^*)。

本コース
葉桜餅 (もち米製)
葉桜(はざくら)とは、桜の花が散り若葉が出始めた頃から新緑で覆われた時期までの桜の木、またはその様を言い、俳句の世界では、夏の季語として用いられます。
花びらが散り始め、同時に若葉が芽吹き始めて新緑の葉の色が混ざり、遠目にくすんで見える頃から、桜の花びらが全て落花し、めしべ・おしべが残って樹木全体に赤みが残っている頃まで、あるいは、樹木全体が新緑の葉で瑞々しく艶を帯びた状態で覆われる頃までです。それ以降の時期で単に葉が茂っている状態の桜を葉桜と呼ぶことはありません。桜の開花状態を示す指標の一分咲き・二分咲きと同様に葉桜では葉と花の割合を示す言葉として満開以降は舞い始め、六分葉桜、七分葉桜、八分葉桜、九分葉桜のように呼ばれます。ん~、いささか難しい(―_―)!!

おまけ。。。
桜の葉の塩漬けについて
木の樽に平たく重ねて入れた桜の葉は塩漬けされ、さくら葉(さくらば)と呼ばれ食用として利用されます。さくら葉はほのかな香りを活かし、桜餅やアイスクリーム、クッキーなどに混ぜ、香り付けの材料として用いられ、好評です。春の桜餅を包む食用のさくら葉は大島桜の葉を用い、静岡県賀茂郡松崎町が日本一の生産量で全国需要の7割を占めています。さくら葉の香りの成分は芳香属化合物のクマリンと呼ばれる精油成分に由来するもので生の葉ではあまり匂いませんが、塩漬けされることで香りが現れます。食用に大島桜が用いられる理由は他の桜に比べてクマリンが多いことによりますが、1876年には人工的にも合成されたそうです。
JAハイナン相良の女性部にて
味噌饅頭
ご存じのとおり、味噌(一部地域は、黒糖)を用いた饅頭です。一般的には「みそまん」と呼ばれ日本全域にあり、地方の銘菓や土産菓子として、定番のおやつとして多くの甘党を魅了しています。餡の甘みと味噌の辛味が合って人気で、どなたも一度はお召し上がりの経験はあろうかと思います。
味噌を生地に入れるタイプ、餡に入れるタイプ、饅頭の色だけが味噌に似ているだけのタイプなどがあり、味・香り・色で味噌の風味を演出します。使用される味噌は色々で、土産菓子などには、製造される地域の特産のものが使われていることが多いです。食感も多様で、薄皮タイプ・ふんわりタイプ・ザラメ糖などを使用する配合もあり、菓子の銘は同じでも、各店では全く違った製品となっていて、これほどに作り手の好みやこだわりが反映される菓子は珍しいかもしれません。

中国からのお客様が日本の伝統文化を遊学の旅
「旧木下邸・勝間田塾にて和菓子作り体験」

旧木下邸

鴬・桜


県営吉田公園緑花大学
お題「さくら」

花筏・桜花 練りきり 小豆漉し餡、桜餡 製


 ふるさと創菓処 扇松堂
ふるさと創菓処 扇松堂
 住所
住所 電話・FAX
電話・FAX 営業時間
営業時間 定休日
定休日  駐車場
駐車場 アクセス
アクセス