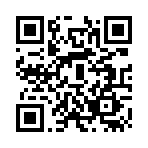2015年05月20日
吉田公園 緑花大学 いと、お菓子!
2015吉田公園緑花大学「いと、お菓子!」
始まってます。
4月開講
お題は「春」

「稚児桜」 「桜花」 の2品
5月
お題は「初夏」

「若楓」 「落とし文」
“落とし文”とは、公然とは言えないことや秘かに想う恋心を伝えるために、伝えたい人の近くに落として拾わせた置手紙のことで、昆虫の「オトシブミ」が葉を丸めて巻物状にして、「時鳥(ホトトギス)の落とし文」とか、「鶯(ウグイス)の落とし文」と呼ばれていたものによく似ていることから名づけられた菓銘です。その姿から小鳥の恋文まで想いを巡らせた先人の発想には、感心させられます。 初夏を表す季語にも使われてます。
始まってます。
4月開講
お題は「春」

「稚児桜」 「桜花」 の2品
5月
お題は「初夏」

「若楓」 「落とし文」
“落とし文”とは、公然とは言えないことや秘かに想う恋心を伝えるために、伝えたい人の近くに落として拾わせた置手紙のことで、昆虫の「オトシブミ」が葉を丸めて巻物状にして、「時鳥(ホトトギス)の落とし文」とか、「鶯(ウグイス)の落とし文」と呼ばれていたものによく似ていることから名づけられた菓銘です。その姿から小鳥の恋文まで想いを巡らせた先人の発想には、感心させられます。 初夏を表す季語にも使われてます。
2015年05月20日
2015 いと、お菓子!
本年度も、牧之原市はりはら塾・扇松堂の「いと、お菓子!」始まってます。
遅ればせの報告で・・・。
4月,
開講・初回講座のご案内
清明、二十四節気五番目の季節です。生きもの全てが、清らかに生命を輝かせるとの意味で、草花が咲き乱れ、鳥や虫が舞い飛び、ぽかぽか陽気に包まれます。
はりはら塾「いと、お菓子!」にご参加いただき有難う御座います。お菓子作りの楽しみと美味しさの窓口を広げて頂けるように応援させて頂きます。食育や自己啓発の場としてもご活用ください。一年間、宜しくお願いいたします。
小習いコース
「紅白饅頭」
はりはら塾2015「いと、お菓子!」小習いコースにようこそ。。。基本的な材料の知識と使い方、技術を身につけて、お好みのお菓子作りへの出発点に。自由な発想で自分だけのお菓子ワールドを広げてください・・。宜しくお願いいたします。
初回は和菓子の定番、「お饅頭」。。。入塾をお祝いして「紅白饅頭」(*^^)vです。紅白の色は、めでたい、お祝い、縁起がよい、といった意味で祝いの席の紅白幕や紅白餅、紅白饅頭など縁起物に用いられています。これは由来に諸説ありますが、赤色が赤ちゃんというように出生を意味し、白色が死装束の色のように死や別れを意味するところから、その 2つの色を組み合わせることによって人生そのものを表しているという説や、花嫁衣裳の色であるという説、古来から赤飯を炊いて祝っていたことから赤飯の色であるという説などが主な由来として知られています。そして、「紅白の饅頭」は花嫁が嫁ぎ先の家風に染まれるように、また、そのまるい形から円満な家庭を築けるようにという願いが込められているとも・・・。
縁起の良いものとして扱われる以外に、紅白歌合戦や、赤白帽、紅白戦など、縁起物意外にも主に「対抗する2組」を表すものとして紅白は用いられます。そのルーツも諸説ありますが、そのひとつに源平合戦とする説があり、源氏が白旗を、平氏が紅旗を掲げて戦ったことが挙げられます。合戦に用いられた配色であり、また、対照的な色合いでもあることから、以来、対抗する配色として用いられるようになったようです。
余談ですが、紅白はなぜ、「コウハク」なのでしょう?赤白(セキハク)とは言わないのでしょうか?それは、漢字の読みにおいて、「セキ」という意味が中国では「赤裸々」「赤貧」などのように「裸」「むき出し」などの悪い意味を持つためです。現代でも中国では「赤」と言う文字は使用せず、あかい意味で「紅」の文字が使われています。

入塾のお祝いに・・・・。
本コース
「よもぎ薯蕷饅頭」
はりはら塾2015「いと、お菓子!」にようこそ。。。
基本的な材料の知識と使い方、技術を身につけて、お好みのお菓子作りや自由な発想のオリジナルお菓子ワールドへ・・、お菓子の楽しさや奥深さを追求してください。宜しくお願いいたします。
「薯蕷饅頭(じょうようまんじゅう)」。。。文字のとおり主材料は薯(いも)!他に、米の粉を特別に加工した薯蕷粉と砂糖。小麦粉を主原料とした小麦饅頭とは異なり、膨張剤は使用せず、薯のコシでふっくらと仕上げます。出来上がりは純白で、着色や成形も比較的自在にでき、米の粉の香りと薯の風味が絶妙で、「上用饅頭」とも表され饅頭の王様と言えます。茶席などで饅頭と言えば通常はこの薯蕷饅頭を意味します。材料の風味がそのまま出来上がりの味を左右するので、夏場はあまり作られません。織部焼きを模した「織部饅頭」、正月用の「えくぼ饅頭」などが定番の仕上げです。
今回は生地に「よもぎ」を混ぜ込んで、季節の薫りと共に楽しみます。「よもぎ」は香りを放って邪気を祓う薬草として、端午の節句等に用いられます。

5月
雑節の八十八夜を過ぎると、もう立夏はすぐそこに。立春から八十八夜までは、春のすべての気が満ちている時間だそうで、その間に育った一番茶は生命力がつまっていて、無病息災・長寿のお茶と言われます。皆さん、新茶はお召し上がりでしょうか?
夏という季節の名前は、一説には「撫づ」が語源だとか。撫でるとは、霊的な生命力を与えるための所作なのだそうです。田植えを済ませた夏の田んぼには、稲を撫でる風が吹き、そよそよと穂波が揺れて、すくすくと育っていきます。
小習いコース
「ババロア・バニーユ」
初夏、汗ばむ季節になると美味しいのが、冷やして食べる冷たいスイーツ。子どもから大人まで広く愛されて、スプーンですくって口に入れた瞬間に、幸せが体中に広がります。
プリンや果汁たっぷりのフルーツゼリー、泡のような口当たりのムースと並んでショーケースに登場するババロア。語源はドイツ南部のババリア(バイエルン)地方に由来。この地方の温かい飲み物で、紅茶やアルコール、シロップ、牛乳などを混ぜ合わせて作ったものがルーツとか。。これをゼリーの考案者でもある19世紀初頭フランスの著名な菓子職人アントナン・カレームがお菓子に作り上げたと言われています。
洋菓子の世界では基本のソース、アングレーズをベースにしたデザート。アングレーズソースとは、牛乳、卵、砂糖を弱火でじっくりと炊き上げて作ったソースで、濃厚な素材の味わいが楽しめるソースです。バニラの香りも贅沢に使ってリッチな味わいを楽しみましょう。
基本の配合をマスターできたら、牛乳をフルーツのピューレに置き換えたり、チョコレート等を加えたりと、いろいろなバリエーションも楽しめます。冷やし固めたババロアに、クレーム・シャンティ、フルーツ等を色とりどりに飾って、見た目にも華やかなデザートに仕上げてみましょう。

本コース
「ラズべり―・カップチーズケーキ」
チーズケーキ発祥の地は古代ギリシャだと言われています。遊牧民の暮らしの中からチーズが生まれ、それがケーキとして発展していったようです。紀元前776年の第1回古代オリンピックの期間中にアスリートに振る舞われたとの記録もあるとか。。。ただし、ギリシャで生まれたチーズケーキは「トリヨン」というプディング風のお菓子で、現在のケーキとは異なるものだったようです。やがてチーズケーキはヨーロッパ各地に普及していくこととなりました。
日本にチーズが渡ったのは奈良時代、そして明治6年の「万宝珍書(ばんほうちんしょ)」には、「ライスチーズケーキ」なるものが紹介され、明治後期の料理本に「チーズソフレー」の記述もあります。ドイツの「ケーゼ(チーズ)・クーヘン(ケーキ)」が元祖だとも言われています。
現在のようなチーズケーキが登場するのは昭和になって、冷蔵庫の開発によってチーズが材料として普及し、クリームチーズと生クリームを合わせてゼラチンで固めた「レアチーズ」が人気を集め、昭和40年代、モロゾフ・ユーハイム・トップスなどの有名メーカーがチーズケーキを作り始めて一大ブームをおこして以来、ケーキの定番の座を守り続けています。
他にも、サブレ生地を敷いたパイ皿にクリームチーズやカッテージチーズ、マスカルポーネと砂糖、卵、生クリームを合わせて流し込み、オーブンで焼いた「ベイクドチーズケーキ」。クリームチーズにメレンゲを加えて湯煎焼きした「スフレチーズケーキ」。フレッシュチーズにメレンゲと生クリーム、砂糖を加えてふんわりと優しい感じに仕上げる「クレーム・アンジェ」等があります。
今回は、ラズベリーピュレのおいしさをたっぷり味わえるレアチーズケーキ。混ぜて、冷やして固めるだけの簡単な工程で作れる絶品レシピです。

遅ればせの報告で・・・。
4月,
開講・初回講座のご案内
清明、二十四節気五番目の季節です。生きもの全てが、清らかに生命を輝かせるとの意味で、草花が咲き乱れ、鳥や虫が舞い飛び、ぽかぽか陽気に包まれます。
はりはら塾「いと、お菓子!」にご参加いただき有難う御座います。お菓子作りの楽しみと美味しさの窓口を広げて頂けるように応援させて頂きます。食育や自己啓発の場としてもご活用ください。一年間、宜しくお願いいたします。
小習いコース
「紅白饅頭」
はりはら塾2015「いと、お菓子!」小習いコースにようこそ。。。基本的な材料の知識と使い方、技術を身につけて、お好みのお菓子作りへの出発点に。自由な発想で自分だけのお菓子ワールドを広げてください・・。宜しくお願いいたします。
初回は和菓子の定番、「お饅頭」。。。入塾をお祝いして「紅白饅頭」(*^^)vです。紅白の色は、めでたい、お祝い、縁起がよい、といった意味で祝いの席の紅白幕や紅白餅、紅白饅頭など縁起物に用いられています。これは由来に諸説ありますが、赤色が赤ちゃんというように出生を意味し、白色が死装束の色のように死や別れを意味するところから、その 2つの色を組み合わせることによって人生そのものを表しているという説や、花嫁衣裳の色であるという説、古来から赤飯を炊いて祝っていたことから赤飯の色であるという説などが主な由来として知られています。そして、「紅白の饅頭」は花嫁が嫁ぎ先の家風に染まれるように、また、そのまるい形から円満な家庭を築けるようにという願いが込められているとも・・・。
縁起の良いものとして扱われる以外に、紅白歌合戦や、赤白帽、紅白戦など、縁起物意外にも主に「対抗する2組」を表すものとして紅白は用いられます。そのルーツも諸説ありますが、そのひとつに源平合戦とする説があり、源氏が白旗を、平氏が紅旗を掲げて戦ったことが挙げられます。合戦に用いられた配色であり、また、対照的な色合いでもあることから、以来、対抗する配色として用いられるようになったようです。
余談ですが、紅白はなぜ、「コウハク」なのでしょう?赤白(セキハク)とは言わないのでしょうか?それは、漢字の読みにおいて、「セキ」という意味が中国では「赤裸々」「赤貧」などのように「裸」「むき出し」などの悪い意味を持つためです。現代でも中国では「赤」と言う文字は使用せず、あかい意味で「紅」の文字が使われています。

入塾のお祝いに・・・・。
本コース
「よもぎ薯蕷饅頭」
はりはら塾2015「いと、お菓子!」にようこそ。。。
基本的な材料の知識と使い方、技術を身につけて、お好みのお菓子作りや自由な発想のオリジナルお菓子ワールドへ・・、お菓子の楽しさや奥深さを追求してください。宜しくお願いいたします。
「薯蕷饅頭(じょうようまんじゅう)」。。。文字のとおり主材料は薯(いも)!他に、米の粉を特別に加工した薯蕷粉と砂糖。小麦粉を主原料とした小麦饅頭とは異なり、膨張剤は使用せず、薯のコシでふっくらと仕上げます。出来上がりは純白で、着色や成形も比較的自在にでき、米の粉の香りと薯の風味が絶妙で、「上用饅頭」とも表され饅頭の王様と言えます。茶席などで饅頭と言えば通常はこの薯蕷饅頭を意味します。材料の風味がそのまま出来上がりの味を左右するので、夏場はあまり作られません。織部焼きを模した「織部饅頭」、正月用の「えくぼ饅頭」などが定番の仕上げです。
今回は生地に「よもぎ」を混ぜ込んで、季節の薫りと共に楽しみます。「よもぎ」は香りを放って邪気を祓う薬草として、端午の節句等に用いられます。

5月
雑節の八十八夜を過ぎると、もう立夏はすぐそこに。立春から八十八夜までは、春のすべての気が満ちている時間だそうで、その間に育った一番茶は生命力がつまっていて、無病息災・長寿のお茶と言われます。皆さん、新茶はお召し上がりでしょうか?
夏という季節の名前は、一説には「撫づ」が語源だとか。撫でるとは、霊的な生命力を与えるための所作なのだそうです。田植えを済ませた夏の田んぼには、稲を撫でる風が吹き、そよそよと穂波が揺れて、すくすくと育っていきます。
小習いコース
「ババロア・バニーユ」
初夏、汗ばむ季節になると美味しいのが、冷やして食べる冷たいスイーツ。子どもから大人まで広く愛されて、スプーンですくって口に入れた瞬間に、幸せが体中に広がります。
プリンや果汁たっぷりのフルーツゼリー、泡のような口当たりのムースと並んでショーケースに登場するババロア。語源はドイツ南部のババリア(バイエルン)地方に由来。この地方の温かい飲み物で、紅茶やアルコール、シロップ、牛乳などを混ぜ合わせて作ったものがルーツとか。。これをゼリーの考案者でもある19世紀初頭フランスの著名な菓子職人アントナン・カレームがお菓子に作り上げたと言われています。
洋菓子の世界では基本のソース、アングレーズをベースにしたデザート。アングレーズソースとは、牛乳、卵、砂糖を弱火でじっくりと炊き上げて作ったソースで、濃厚な素材の味わいが楽しめるソースです。バニラの香りも贅沢に使ってリッチな味わいを楽しみましょう。
基本の配合をマスターできたら、牛乳をフルーツのピューレに置き換えたり、チョコレート等を加えたりと、いろいろなバリエーションも楽しめます。冷やし固めたババロアに、クレーム・シャンティ、フルーツ等を色とりどりに飾って、見た目にも華やかなデザートに仕上げてみましょう。

本コース
「ラズべり―・カップチーズケーキ」
チーズケーキ発祥の地は古代ギリシャだと言われています。遊牧民の暮らしの中からチーズが生まれ、それがケーキとして発展していったようです。紀元前776年の第1回古代オリンピックの期間中にアスリートに振る舞われたとの記録もあるとか。。。ただし、ギリシャで生まれたチーズケーキは「トリヨン」というプディング風のお菓子で、現在のケーキとは異なるものだったようです。やがてチーズケーキはヨーロッパ各地に普及していくこととなりました。
日本にチーズが渡ったのは奈良時代、そして明治6年の「万宝珍書(ばんほうちんしょ)」には、「ライスチーズケーキ」なるものが紹介され、明治後期の料理本に「チーズソフレー」の記述もあります。ドイツの「ケーゼ(チーズ)・クーヘン(ケーキ)」が元祖だとも言われています。
現在のようなチーズケーキが登場するのは昭和になって、冷蔵庫の開発によってチーズが材料として普及し、クリームチーズと生クリームを合わせてゼラチンで固めた「レアチーズ」が人気を集め、昭和40年代、モロゾフ・ユーハイム・トップスなどの有名メーカーがチーズケーキを作り始めて一大ブームをおこして以来、ケーキの定番の座を守り続けています。
他にも、サブレ生地を敷いたパイ皿にクリームチーズやカッテージチーズ、マスカルポーネと砂糖、卵、生クリームを合わせて流し込み、オーブンで焼いた「ベイクドチーズケーキ」。クリームチーズにメレンゲを加えて湯煎焼きした「スフレチーズケーキ」。フレッシュチーズにメレンゲと生クリーム、砂糖を加えてふんわりと優しい感じに仕上げる「クレーム・アンジェ」等があります。
今回は、ラズベリーピュレのおいしさをたっぷり味わえるレアチーズケーキ。混ぜて、冷やして固めるだけの簡単な工程で作れる絶品レシピです。



 ふるさと創菓処 扇松堂
ふるさと創菓処 扇松堂
 住所
住所 電話・FAX
電話・FAX 営業時間
営業時間 定休日
定休日  駐車場
駐車場 アクセス
アクセス