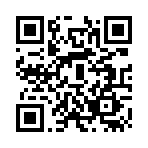2015年08月19日
8月のいと、お菓子!
8月 講座のご案内
灼熱の太陽が降り注ぐ中、24節気では「立秋」。暑さに耐える毎日ですが、この後の暑さは「残暑」と呼び名も変わります。
実際に、朝夕の風が涼しく感じたり、鳴く蝉がアブラゼミからヒグラシに、入道雲が鰯雲に変化してきます。初めてその季節らしさを感じる空を「初空」といいます。昔から人々は、空を見上げながら、めぐる季節を感じていたのでしょう。
「秋」の語源は、収穫が「飽(あ)き」満ちる、空が「清明(あきらか)」、草木の葉が「紅(あか)く」なる・・などの諸説がありますが、いずれにしても豊かな日本の秋の情景から生まれた言葉には間違いありません。
11日
県営吉田公園緑花大学「いと、お菓子」
お題は「残暑」

薄赤の練りきりを錦玉羹で包みこんで「水牡丹」、練りきり製「撫子」
はりはら塾「いと、お菓子!」
葛粉を使用した和菓子
葛粉は、クズの根から製造した澱粉です。各種デンプンのうち、もっとも良質とされている。吉野(奈良県)の国栖(くず)で生産されるものが有名で、吉野葛の名がある。他に、福岡県の筑前(ちくぜん)葛、三重県の伊勢(いせ)葛、福井県の若狭(わかさ)葛が有名である。またクズの語自体、国栖に由来するとも説かれる。
秋の終わりから初春にかけて発芽前に根を掘り起こし、よく水洗いして平石の上で砕く。これをザルに入れて水槽の中でかき混ぜ、デンプンを洗い出す。デンプン液は、細かい繊維などを除くため、さらに布袋に入れて漉す。静置するとデンプンが沈殿するので、上澄み液を捨て、デンプンが純白になるまで水さらしを繰り返す。十分さらしたデンプンの水分を除き、適当な大きさに砕いて乾燥する。このために葛粉は不ぞろいの塊状をしている。なお、葛粉は前述のとおり、生産には手間がかかり生産量が少なく高価なため、市販の葛粉と称するものは各種澱粉を混合してあることがある。
葛粉を少量の水で溶き、これに熱湯を加えた葛湯は、病人や小児の栄養食として昔から重用されている。葛餅(くずもち)、葛ちまき、葛そうめんなどは、以前に補食として用いられた名残(なごり)である。また漢方のかぜ薬である葛根湯(かっこんとう)の主成分はこの葛根である。菓子では、葛桜、葛まんじゅう、葛切り、葛ちまきなどの原料として用いられている。透明感のある生地は見るからに涼しげで、ひんやりつるんとした口当たりが楽しめる。
13日、小習いコース「葛焼き」
「葛焼き」は、柔らかい食感となめらかな口どけが特徴で、透明感のある姿から夏向きの和菓子とされます。このように、葛を焼くのは関西の発想で、関東ではほとんど見かける事はない技法です。ガラス等の器で涼しげな感じを強調して残暑を乗り切りませうぅぅぅぅ。

17日、本コース「葛まんじゅう」
葛粉の生地で餡を包むのは、通常の饅頭とは少々勝手が違います。生地の切り分けや包餡には、いつも以上に優しく生地を扱って、生地の中央に餡を置くイメージをしながら、見栄えのいい葛まんじゅうを目指して挑戦してください、、、、ませ。。。。(*^^)v何事も挑戦です!!!!

レモン餡と小豆漉し餡の2種
灼熱の太陽が降り注ぐ中、24節気では「立秋」。暑さに耐える毎日ですが、この後の暑さは「残暑」と呼び名も変わります。
実際に、朝夕の風が涼しく感じたり、鳴く蝉がアブラゼミからヒグラシに、入道雲が鰯雲に変化してきます。初めてその季節らしさを感じる空を「初空」といいます。昔から人々は、空を見上げながら、めぐる季節を感じていたのでしょう。
「秋」の語源は、収穫が「飽(あ)き」満ちる、空が「清明(あきらか)」、草木の葉が「紅(あか)く」なる・・などの諸説がありますが、いずれにしても豊かな日本の秋の情景から生まれた言葉には間違いありません。
11日
県営吉田公園緑花大学「いと、お菓子」
お題は「残暑」

薄赤の練りきりを錦玉羹で包みこんで「水牡丹」、練りきり製「撫子」
はりはら塾「いと、お菓子!」
葛粉を使用した和菓子
葛粉は、クズの根から製造した澱粉です。各種デンプンのうち、もっとも良質とされている。吉野(奈良県)の国栖(くず)で生産されるものが有名で、吉野葛の名がある。他に、福岡県の筑前(ちくぜん)葛、三重県の伊勢(いせ)葛、福井県の若狭(わかさ)葛が有名である。またクズの語自体、国栖に由来するとも説かれる。
秋の終わりから初春にかけて発芽前に根を掘り起こし、よく水洗いして平石の上で砕く。これをザルに入れて水槽の中でかき混ぜ、デンプンを洗い出す。デンプン液は、細かい繊維などを除くため、さらに布袋に入れて漉す。静置するとデンプンが沈殿するので、上澄み液を捨て、デンプンが純白になるまで水さらしを繰り返す。十分さらしたデンプンの水分を除き、適当な大きさに砕いて乾燥する。このために葛粉は不ぞろいの塊状をしている。なお、葛粉は前述のとおり、生産には手間がかかり生産量が少なく高価なため、市販の葛粉と称するものは各種澱粉を混合してあることがある。
葛粉を少量の水で溶き、これに熱湯を加えた葛湯は、病人や小児の栄養食として昔から重用されている。葛餅(くずもち)、葛ちまき、葛そうめんなどは、以前に補食として用いられた名残(なごり)である。また漢方のかぜ薬である葛根湯(かっこんとう)の主成分はこの葛根である。菓子では、葛桜、葛まんじゅう、葛切り、葛ちまきなどの原料として用いられている。透明感のある生地は見るからに涼しげで、ひんやりつるんとした口当たりが楽しめる。
13日、小習いコース「葛焼き」
「葛焼き」は、柔らかい食感となめらかな口どけが特徴で、透明感のある姿から夏向きの和菓子とされます。このように、葛を焼くのは関西の発想で、関東ではほとんど見かける事はない技法です。ガラス等の器で涼しげな感じを強調して残暑を乗り切りませうぅぅぅぅ。

17日、本コース「葛まんじゅう」
葛粉の生地で餡を包むのは、通常の饅頭とは少々勝手が違います。生地の切り分けや包餡には、いつも以上に優しく生地を扱って、生地の中央に餡を置くイメージをしながら、見栄えのいい葛まんじゅうを目指して挑戦してください、、、、ませ。。。。(*^^)v何事も挑戦です!!!!

レモン餡と小豆漉し餡の2種


 ふるさと創菓処 扇松堂
ふるさと創菓処 扇松堂
 住所
住所 電話・FAX
電話・FAX 営業時間
営業時間 定休日
定休日  駐車場
駐車場 アクセス
アクセス