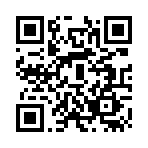2017年10月22日
10月の「いと、お菓子!」
ご案内
季節ごとに同じ事を繰り返すのが、家庭の行事。一度あることは二度・・。そこで、後に来る行事は「のちの・・」をつけて区別します。初夏の衣替えに対して、秋は「のちの衣替え」、菊の節句は「のちの雛」、里帰りを意味する藪入りは、正月に対してお盆は「のちの藪入り」。十五夜のお月見に続く十三夜は「のちの月見」。「のちの・・・」という語感がなんとも優しげです。
はりはら塾
味噌饅頭
饅頭は小麦粉やそば粉などの粉類を練った生地で餡を包み、蒸したり焼いたりした菓子です。漢字の「饅頭(マントウ)」は漢語で、「頭」を唐音読みして「マンジュウ」となった。起源は中国に有り、諸葛孔明が南征した際、川の神に人身御供として人の頭を捧げれば鎮まるという習慣を改めるために、羊や豚の肉を小麦粉で作った皮でくるんだ物を人頭に見立て、神に捧げたことが由来です。日本では1349年に宋から渡来した林浄因が奈良で作った事が始まりと言われている。
味噌(一部地域は、黒糖)を用いた饅頭を「味噌饅頭」。一般的には「みそまん」と呼ばれ日本全域にあり、餡の甘みと味噌の辛味が合って人気で、地方の銘菓や土産菓子、定番のおやつとして多くの甘党を魅了しています。味噌を生地に入れるタイプ、餡に入れるタイプ、饅頭の色だけが味噌に似ているだけのタイプなどがあり、味・香り・色で味噌の風味を演出します。使用される味噌は色々で、土産菓子などには、製造される地域の特産のものが使われていることが多いです。食感も多様で、薄皮タイプ・ふんわりタイプ・ザラメ糖などを使用する配合もあり、菓子の銘は同じでも、各店では全く違った製品となっていて、これほどに作り手の好みやこだわりが反映される菓子は珍しいかもしれません。

手亡餡、小豆漉し餡
吉田公園「緑花大学」
お題「仲秋」

こぼれ萩・紅葉 煉りきり製 山路 浮島製
季節ごとに同じ事を繰り返すのが、家庭の行事。一度あることは二度・・。そこで、後に来る行事は「のちの・・」をつけて区別します。初夏の衣替えに対して、秋は「のちの衣替え」、菊の節句は「のちの雛」、里帰りを意味する藪入りは、正月に対してお盆は「のちの藪入り」。十五夜のお月見に続く十三夜は「のちの月見」。「のちの・・・」という語感がなんとも優しげです。
はりはら塾
味噌饅頭
饅頭は小麦粉やそば粉などの粉類を練った生地で餡を包み、蒸したり焼いたりした菓子です。漢字の「饅頭(マントウ)」は漢語で、「頭」を唐音読みして「マンジュウ」となった。起源は中国に有り、諸葛孔明が南征した際、川の神に人身御供として人の頭を捧げれば鎮まるという習慣を改めるために、羊や豚の肉を小麦粉で作った皮でくるんだ物を人頭に見立て、神に捧げたことが由来です。日本では1349年に宋から渡来した林浄因が奈良で作った事が始まりと言われている。
味噌(一部地域は、黒糖)を用いた饅頭を「味噌饅頭」。一般的には「みそまん」と呼ばれ日本全域にあり、餡の甘みと味噌の辛味が合って人気で、地方の銘菓や土産菓子、定番のおやつとして多くの甘党を魅了しています。味噌を生地に入れるタイプ、餡に入れるタイプ、饅頭の色だけが味噌に似ているだけのタイプなどがあり、味・香り・色で味噌の風味を演出します。使用される味噌は色々で、土産菓子などには、製造される地域の特産のものが使われていることが多いです。食感も多様で、薄皮タイプ・ふんわりタイプ・ザラメ糖などを使用する配合もあり、菓子の銘は同じでも、各店では全く違った製品となっていて、これほどに作り手の好みやこだわりが反映される菓子は珍しいかもしれません。

手亡餡、小豆漉し餡
吉田公園「緑花大学」
お題「仲秋」

こぼれ萩・紅葉 煉りきり製 山路 浮島製


 ふるさと創菓処 扇松堂
ふるさと創菓処 扇松堂
 住所
住所 電話・FAX
電話・FAX 営業時間
営業時間 定休日
定休日  駐車場
駐車場 アクセス
アクセス