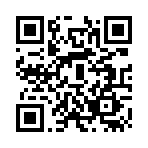2019年11月06日
いと、お菓子!2019 10月
ご案内
「寒露」露が冷たく感じられる頃です。山は、巡る季節に刻々と表情を変えていきます。春「山笑う」、夏「山滴る」、秋「山装(粧)う」、冬「山眠る」。中国の画家・郭熙(かくき)の詩から作られた山の季語です。冷えていく空気の中、上の方から徐々に赤や黄色の錦を装い始めた景色に囲まれます。太陽があっという間に沈んでしまう様を「つるべ落とし」、旧暦9月が長月のとおり、どんどん夜が長くなり、秋の夜長を楽しむ季節の始まりです。
はりはら塾「いと、お菓子!」
ホクホク新栗の蒸し羊羹
羊羹の「羊」はひつじ、「羹」はあつものという漢字からなるように、本来は羊肉を使用した、とろみある汁物のことを指す言葉です。これは中国の古い点心のひとつで、鎌倉時代に中国に渡った僧侶が、日本にこの文化をもたらしたようです。ただ当時、仏教では肉食を禁じていたうえ、日本でも羊を食べる文化があまりなかったことから、色合いが似た小豆や葛粉などを使用して、中国の羊羹に見立てた料理を作ったのがはじまりだと言われています。
羊羹とは総称で、練り羊羹、水羊羹、蒸し羊羹に分けることができ、我々が一般的に羊羹と呼んでいるものは、練り羊羹のこと。この3つのなかで最も歴史が古いものは、蒸し羊羹で、次いで練り羊羹、水羊羹と続く。練り羊羹が誕生したのは江戸時代の後期、1862年には、現在でも続く老舗和菓子店で羊羹が作られていた記録が残っている。練り羊羹に使われているのは、小豆、砂糖、そして寒天。寒天を溶かした水に、小豆を炊いた餡と砂糖を入れて練ることから、練り羊羹と呼ばれます。水羊羹は、古くは葛や小麦粉を使って蒸し羊羹のように作られていたようですが、現在では寒天を使って作られることがほとんど。この寒天を使用した水羊羹が一般に広まったのは明治以降で、材料は練り羊羹とほぼ同じでも、大きな違いは糖度と食感にあります。
さて、蒸し羊羹は、羊羹のなかでももっとも歴史が古く、小麦粉や葛粉、片栗粉、上新粉などを使い、蒸すことで固めるものである。現在では材料にもアレンジされたものが主流で、栗蒸し羊羹や芋羊羹などが有名です。
初夏に独特の匂いを漂わせた栗の花も、秋が進むにつれて実を結び毬栗が大きくなっていきます。青い毬に包まれた「若栗」、実が熟して「笑栗」、梢から落ちて「落栗」、そんな秋の味覚を美味しく頂くには・・・コレ!。

菊4種 練り切り製 と栗蒸し羊羹
吉田公園緑化大学
お題「仲秋」

着せ綿・初紅葉 新栗蒸し羊羹
「寒露」露が冷たく感じられる頃です。山は、巡る季節に刻々と表情を変えていきます。春「山笑う」、夏「山滴る」、秋「山装(粧)う」、冬「山眠る」。中国の画家・郭熙(かくき)の詩から作られた山の季語です。冷えていく空気の中、上の方から徐々に赤や黄色の錦を装い始めた景色に囲まれます。太陽があっという間に沈んでしまう様を「つるべ落とし」、旧暦9月が長月のとおり、どんどん夜が長くなり、秋の夜長を楽しむ季節の始まりです。
はりはら塾「いと、お菓子!」
ホクホク新栗の蒸し羊羹
羊羹の「羊」はひつじ、「羹」はあつものという漢字からなるように、本来は羊肉を使用した、とろみある汁物のことを指す言葉です。これは中国の古い点心のひとつで、鎌倉時代に中国に渡った僧侶が、日本にこの文化をもたらしたようです。ただ当時、仏教では肉食を禁じていたうえ、日本でも羊を食べる文化があまりなかったことから、色合いが似た小豆や葛粉などを使用して、中国の羊羹に見立てた料理を作ったのがはじまりだと言われています。
羊羹とは総称で、練り羊羹、水羊羹、蒸し羊羹に分けることができ、我々が一般的に羊羹と呼んでいるものは、練り羊羹のこと。この3つのなかで最も歴史が古いものは、蒸し羊羹で、次いで練り羊羹、水羊羹と続く。練り羊羹が誕生したのは江戸時代の後期、1862年には、現在でも続く老舗和菓子店で羊羹が作られていた記録が残っている。練り羊羹に使われているのは、小豆、砂糖、そして寒天。寒天を溶かした水に、小豆を炊いた餡と砂糖を入れて練ることから、練り羊羹と呼ばれます。水羊羹は、古くは葛や小麦粉を使って蒸し羊羹のように作られていたようですが、現在では寒天を使って作られることがほとんど。この寒天を使用した水羊羹が一般に広まったのは明治以降で、材料は練り羊羹とほぼ同じでも、大きな違いは糖度と食感にあります。
さて、蒸し羊羹は、羊羹のなかでももっとも歴史が古く、小麦粉や葛粉、片栗粉、上新粉などを使い、蒸すことで固めるものである。現在では材料にもアレンジされたものが主流で、栗蒸し羊羹や芋羊羹などが有名です。
初夏に独特の匂いを漂わせた栗の花も、秋が進むにつれて実を結び毬栗が大きくなっていきます。青い毬に包まれた「若栗」、実が熟して「笑栗」、梢から落ちて「落栗」、そんな秋の味覚を美味しく頂くには・・・コレ!。

菊4種 練り切り製 と栗蒸し羊羹
吉田公園緑化大学
お題「仲秋」

着せ綿・初紅葉 新栗蒸し羊羹


 ふるさと創菓処 扇松堂
ふるさと創菓処 扇松堂
 住所
住所 電話・FAX
電話・FAX 営業時間
営業時間 定休日
定休日  駐車場
駐車場 アクセス
アクセス