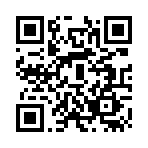2012年09月18日
仲秋と中秋
今月の30日には満月が観られます。
中秋の名月を「仲秋の名月」と書いているところもありますが、この「中秋」と「仲秋」、何が違うのか・・・?
調べてみると、
仲秋…《秋の三ヶ月(七・八・九)の中の意》陰暦八月の別称。なかのあき。
中秋…陰暦八月十五日。「--の名月」
中秋の名月は、陰暦(旧暦)で8月15日、つまり秋の真ん中の日の月のことを指します。従って、陰暦8月15日を示す「中秋」という言葉の方がふさわしいことになります。
仲秋という言葉は、旧暦で8月を示す言葉の1つです。もともと旧暦の月の呼び方の中に、季節の真ん中の月(春なら2月、夏なら5月、秋なら9月、冬なら11月)に「仲」をつけて呼ぶ言葉があります。例えば、「仲春」といえば2月、「仲夏」といえば5月となります。もちろん、「仲冬」という言い方もあり、これは11月を指します。
「名月」という言葉を「満月」と解釈すれば、「仲秋の名月」でも間違いとはいえなくなりますが、もともとの「8月15日の月」という言葉からすると、「仲秋の名月」よりは、「中秋の名月」の方がより正しい、ということがいえると思います。
もっとも、この「仲秋」と「中秋」は、長い歴史の中でだんだん区別されずに使われてきているようにもみえます。「広辞苑」第4版をみてみますと、「中秋」と「仲秋」は同じ言葉として扱われています。
まあ、「月より団子」(笑)を生業としてますので堅苦しいのも・・・・、
月見を題にお茶会もあちらこちらで催されるようです。

菓銘は 右上 萩の月 黒ゴマ入りの練りきり餡に黄身餡を包んで、切り口にお月様が顔を出します。
右下 満月 黄身餡のソボロに小豆粒餡を包み、シナモンでススキ印を。
左上 月明かり 小豆皮むき餡の浮島とカボチャ羊羹の組み合わせ。
左下 芋名月 薯蕷饅頭製
中秋の名月を「仲秋の名月」と書いているところもありますが、この「中秋」と「仲秋」、何が違うのか・・・?
調べてみると、
仲秋…《秋の三ヶ月(七・八・九)の中の意》陰暦八月の別称。なかのあき。
中秋…陰暦八月十五日。「--の名月」
中秋の名月は、陰暦(旧暦)で8月15日、つまり秋の真ん中の日の月のことを指します。従って、陰暦8月15日を示す「中秋」という言葉の方がふさわしいことになります。
仲秋という言葉は、旧暦で8月を示す言葉の1つです。もともと旧暦の月の呼び方の中に、季節の真ん中の月(春なら2月、夏なら5月、秋なら9月、冬なら11月)に「仲」をつけて呼ぶ言葉があります。例えば、「仲春」といえば2月、「仲夏」といえば5月となります。もちろん、「仲冬」という言い方もあり、これは11月を指します。
「名月」という言葉を「満月」と解釈すれば、「仲秋の名月」でも間違いとはいえなくなりますが、もともとの「8月15日の月」という言葉からすると、「仲秋の名月」よりは、「中秋の名月」の方がより正しい、ということがいえると思います。
もっとも、この「仲秋」と「中秋」は、長い歴史の中でだんだん区別されずに使われてきているようにもみえます。「広辞苑」第4版をみてみますと、「中秋」と「仲秋」は同じ言葉として扱われています。
まあ、「月より団子」(笑)を生業としてますので堅苦しいのも・・・・、
月見を題にお茶会もあちらこちらで催されるようです。

菓銘は 右上 萩の月 黒ゴマ入りの練りきり餡に黄身餡を包んで、切り口にお月様が顔を出します。
右下 満月 黄身餡のソボロに小豆粒餡を包み、シナモンでススキ印を。
左上 月明かり 小豆皮むき餡の浮島とカボチャ羊羹の組み合わせ。
左下 芋名月 薯蕷饅頭製
Posted by 扇松DO at 02:04│Comments(0)
│茶席菓子







 ふるさと創菓処 扇松堂
ふるさと創菓処 扇松堂
 住所
住所 電話・FAX
電話・FAX 営業時間
営業時間 定休日
定休日  駐車場
駐車場 アクセス
アクセス