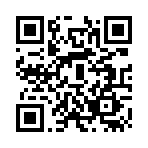2013年06月19日
2013年06月19日
はりはら塾 初夏の和菓子
第3回講座のご案内
水無月。麦秋のみぎり、いかがお過ごしでしょうか。
暦では立春から数えて135日目が入梅、今年は例年よりも早く「梅雨入り宣言」の発表があり、体調管理にも注意が必要です。掃晴娘(雨雲をホウキで掃く晴れ娘)が活躍してくれると助かります。
和服の世界では袷と一重を切り替える「更衣(ころもがえ)」のとき。これからは、ひんやり・さっぱりの暑気払いの冷菓が好まれます。甘く食べやすいお菓子でエネルギーを補給して、厳しい暑さと夏の体力の消耗に備えましょう。
小習いコースは。。。。。
水ようかん
梅雨、お見舞い申し上げます。
夏の和菓子の定番「水羊羹」。。夏菓子の醍醐味を存分に味わいたいならば、水羊羹に行きつくのでは…?滑らかな口解けと、ひんやりとした優しい喉ごしが身上で、小豆の風味をストレートに味わえます。シンプルな配合ですので素材の良し悪しと煮詰め濃度が大切。。
和菓子に用いられる代表的な凝固剤が「寒天」。天然寒天は、天草などの紅藻類から寒天質を抽出し、凝固、自然凍結乾燥して作られます。棒状の「角寒天」、紐状の「糸寒天」、フレーク状などがあります。その他に、工業寒天は固形と粉末があり、用途によって凝固力や弾力が違って、味わいが変わります。

それぞれの個性ある練りきり製の朝顔も咲いて

本コースは。。。。。
葉桜餅
葉桜(はざくら)とは、桜の花が散り若葉が出始めた頃から新緑で覆われた時期までの桜の木、またはその様を言い、俳句の世界では、夏の季語として用いられます。
花びらが散り始め、同時に若葉が芽吹き始めて新緑の葉の色が混ざり、遠目にくすんで見える頃から、桜の花びらが全て落花し、めしべ・おしべが残って樹木全体に赤みが残っている頃まで、あるいは、樹木全体が新緑の葉で瑞々しく艶を帯びた状態で覆われる頃までです。それ以降の時期で単に葉が茂っている状態の桜を葉桜と呼ぶことはありません。桜の開花状態を示す指標の一分咲き・二分咲きと同様に葉桜では葉と花の割合を示す言葉として満開以降は舞い始め、六分葉桜、七分葉桜、八分葉桜、九分葉桜のように呼ばれます。いささか難しい!!
木の樽に平たく重ねて入れた桜の葉は塩漬けされ、さくら葉(さくらば)と呼ばれ食用として利用されます。さくら葉はほのかな香りを活かし、桜餅やアイスクリーム、クッキーなどに混ぜ、香り付けの材料として用いられ、好評です。春の桜餅を包む食用のさくら葉は大島桜の葉を用い、静岡県賀茂郡松崎町が日本一の生産量で全国需要の7割を占めています。さくら葉の香りの成分は芳香属化合物のクマリンと呼ばれる精油成分に由来するもので生の葉ではあまり匂いませんが、塩漬けされることで香りが現れます。食用に大島桜が用いられる理由は他の桜に比べてクマリンが多いことによりますが、1876年には人工的にも合成されたそうです。

水無月。麦秋のみぎり、いかがお過ごしでしょうか。
暦では立春から数えて135日目が入梅、今年は例年よりも早く「梅雨入り宣言」の発表があり、体調管理にも注意が必要です。掃晴娘(雨雲をホウキで掃く晴れ娘)が活躍してくれると助かります。
和服の世界では袷と一重を切り替える「更衣(ころもがえ)」のとき。これからは、ひんやり・さっぱりの暑気払いの冷菓が好まれます。甘く食べやすいお菓子でエネルギーを補給して、厳しい暑さと夏の体力の消耗に備えましょう。
小習いコースは。。。。。
水ようかん
梅雨、お見舞い申し上げます。
夏の和菓子の定番「水羊羹」。。夏菓子の醍醐味を存分に味わいたいならば、水羊羹に行きつくのでは…?滑らかな口解けと、ひんやりとした優しい喉ごしが身上で、小豆の風味をストレートに味わえます。シンプルな配合ですので素材の良し悪しと煮詰め濃度が大切。。
和菓子に用いられる代表的な凝固剤が「寒天」。天然寒天は、天草などの紅藻類から寒天質を抽出し、凝固、自然凍結乾燥して作られます。棒状の「角寒天」、紐状の「糸寒天」、フレーク状などがあります。その他に、工業寒天は固形と粉末があり、用途によって凝固力や弾力が違って、味わいが変わります。

それぞれの個性ある練りきり製の朝顔も咲いて

本コースは。。。。。
葉桜餅
葉桜(はざくら)とは、桜の花が散り若葉が出始めた頃から新緑で覆われた時期までの桜の木、またはその様を言い、俳句の世界では、夏の季語として用いられます。
花びらが散り始め、同時に若葉が芽吹き始めて新緑の葉の色が混ざり、遠目にくすんで見える頃から、桜の花びらが全て落花し、めしべ・おしべが残って樹木全体に赤みが残っている頃まで、あるいは、樹木全体が新緑の葉で瑞々しく艶を帯びた状態で覆われる頃までです。それ以降の時期で単に葉が茂っている状態の桜を葉桜と呼ぶことはありません。桜の開花状態を示す指標の一分咲き・二分咲きと同様に葉桜では葉と花の割合を示す言葉として満開以降は舞い始め、六分葉桜、七分葉桜、八分葉桜、九分葉桜のように呼ばれます。いささか難しい!!
木の樽に平たく重ねて入れた桜の葉は塩漬けされ、さくら葉(さくらば)と呼ばれ食用として利用されます。さくら葉はほのかな香りを活かし、桜餅やアイスクリーム、クッキーなどに混ぜ、香り付けの材料として用いられ、好評です。春の桜餅を包む食用のさくら葉は大島桜の葉を用い、静岡県賀茂郡松崎町が日本一の生産量で全国需要の7割を占めています。さくら葉の香りの成分は芳香属化合物のクマリンと呼ばれる精油成分に由来するもので生の葉ではあまり匂いませんが、塩漬けされることで香りが現れます。食用に大島桜が用いられる理由は他の桜に比べてクマリンが多いことによりますが、1876年には人工的にも合成されたそうです。





 ふるさと創菓処 扇松堂
ふるさと創菓処 扇松堂
 住所
住所 電話・FAX
電話・FAX 営業時間
営業時間 定休日
定休日  駐車場
駐車場 アクセス
アクセス