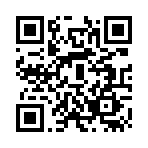2015年07月11日
6月 いと、お菓子!
6月の講座をまとめて・・。
「腐れたる草螢となる」ホタルは腐った草が変身して現れる、と表現されます。落ち葉がたまった水辺で、しっとりとした闇の中から優しい光が浮かび上がる様子を、先人がこのように想像したのかもしれません。ホタルの生育には、低温で流麗な水、豊富なカワニナ、やわらかな土壌、程良い木陰など多くの条件とバランスが必要です。日本の自然の、なんと細やかで巧妙なことか・・・、ホタルが教えてくれているようです。
県営吉田公園「緑花大学」いとお菓子!
お題は「梅雨」
「紫陽花」と「葉の雫」

はりはら塾
小習いコース「水羊羹」
古く「羊羹」とは、中国の料理で、読んで字のごとく羊の羹(あつもの)、つまりは羊の肉を煮たスープの類でした。冷めることで肉のゼラチンによって固まり、自然に煮凝りの状態となる。鎌倉時代から室町時代に、禅僧によって日本に伝えられたが、禅宗では肉食が戒律(五戒)により禁じられているため、精進料理として羊肉の代わりに小豆を用いたものが、日本における羊羹の原型とされています。
羊羹は、小豆を小麦粉または葛粉と混ぜて作る「蒸し羊羹」が始まりです。蒸し羊羹からは、芋羊羹やういろうが派生します。また、当時は砂糖が国産できなかったために大変貴重であり、一般的な羊羹の味付けには甘葛などが用いられることが多く、砂糖を用いた羊羹は特に「砂糖羊羹」。17世紀以後琉球王国や奄美群島などで黒砂糖の生産が開始されて薩摩藩によって日本本土に持ち込まれると、砂糖が用いられるのが一般的になり、甘葛を用いる製法は廃れていきます。
「練り羊羹」が日本の歴史に登場するのは慶長4年(1599年)で、鶴屋(後に駿河屋と改名)の五代目、善右衛門がテングサ(寒天の原料)・粗糖・小豆あんを用いて炊き上げる煉羊羹を開発したものが広まってからです。(他説あり)
当初、水羊羹(みずようかん)は、御節料理の料理菓子として冬の時季に作られたとか。御節料理としては、全国的にその風習も忘れられ、冷蔵技術の普及と嗜好の変化から通年化の傾向により、現在は主に夏に冷やして食されることが多いですが、地域によっては「こたつ羊羹」などとも呼ばれて、冬の寒い時期にしかお目見えしない水羊羹もあります。おこたに入って食べる、採れたて新豆の「こたつ羊羹」も、また格別の味わいでしょうか。
流し箱タイプのほか、アルミ缶やプラスチックカップに入った製品が市販され、高級和菓子店では棹物として、竹筒に入った製品なども販売されています。
夏の和菓子の定番「水羊羹」。。夏菓子の醍醐味を存分に味わいたいならば、水羊羹に行きつくのでは…?滑らかな口解けと、ひんやりとした優しい喉ごしが身上です。小豆の風味をストレートに味わうシンプルな配合ですので、素材の良し悪しと煮詰め濃度が大切です
今回は、近所の山で若竹を調達して・・・。

カットもなかなかの重労働

準備OKです。

で、・・・・出来上がりが。。。
「竹筒水羊羹」

本コース「青梅」
この時期は、二十四節気では芒種、七十二候ではその末候を「梅の子(み)黄ばむ」。梅の実が黄色く色づくとの意味です。旧暦では、立春から数えて百二十七日目を入梅(今年は6/11)としていて、この時期に降る雨なので「梅雨」という名が付いたとも言われています。
梅雨時の茶会の定番菓子銘の「青梅」。東京都の北西部には「青梅(おうめ)市」が存在します。市内の天ヶ瀬(あまがせ)という所に「金剛寺」というお寺があり、中庭に、石柱に囲まれた梅の老木があります。「将門誓いの梅」と呼ばれ、これが「青梅」という地名の由来になった梅の木と云われます。地名の起こりは諸説ありますが、この「将門誓いの梅」説が多くの人々に知られています。承平年間、平将門がこの地を訪れた際、馬の鞭に使用していた梅の枝を自ら地に挿し、「我願い成就あらば栄ふべし。しからずば枯れよかし」と願をかけたところ、見事に梅の枝は根付きました。ところが、この梅の木は実をつけるのですが、夏を過ぎても青いまま熟さずに、また、地に落ちることもなく枝に残っていました。当時の人々はこれを不思議に思い、この地を青梅と呼ぶようになったと伝えられます。「将門誓いの梅」は老木ですが、現在でもいくつかの実をつけ、秋になっても青い実を枝に残しているのを見ることができるようです。
さて、「外郎(ういろう)」とは室町時代の中国の黒い丸薬「透頂香(とうちんこう)」の日本名。とても苦かったので、口直しとして米粉と黒糖を混ぜて作られた菓子が外郎菓子の始まりです。棹物として有名ですが、今回は生地を青緑色に着色し、梅入りの白餡を包んで青梅に成形します。姿形は正に青梅、甘酸っぱい梅餡で梅雨時期でも美味しいお茶タイムを如何でしょうか?
尖った部分とおへその両方を形づくって。。

「腐れたる草螢となる」ホタルは腐った草が変身して現れる、と表現されます。落ち葉がたまった水辺で、しっとりとした闇の中から優しい光が浮かび上がる様子を、先人がこのように想像したのかもしれません。ホタルの生育には、低温で流麗な水、豊富なカワニナ、やわらかな土壌、程良い木陰など多くの条件とバランスが必要です。日本の自然の、なんと細やかで巧妙なことか・・・、ホタルが教えてくれているようです。
県営吉田公園「緑花大学」いとお菓子!
お題は「梅雨」
「紫陽花」と「葉の雫」

はりはら塾
小習いコース「水羊羹」
古く「羊羹」とは、中国の料理で、読んで字のごとく羊の羹(あつもの)、つまりは羊の肉を煮たスープの類でした。冷めることで肉のゼラチンによって固まり、自然に煮凝りの状態となる。鎌倉時代から室町時代に、禅僧によって日本に伝えられたが、禅宗では肉食が戒律(五戒)により禁じられているため、精進料理として羊肉の代わりに小豆を用いたものが、日本における羊羹の原型とされています。
羊羹は、小豆を小麦粉または葛粉と混ぜて作る「蒸し羊羹」が始まりです。蒸し羊羹からは、芋羊羹やういろうが派生します。また、当時は砂糖が国産できなかったために大変貴重であり、一般的な羊羹の味付けには甘葛などが用いられることが多く、砂糖を用いた羊羹は特に「砂糖羊羹」。17世紀以後琉球王国や奄美群島などで黒砂糖の生産が開始されて薩摩藩によって日本本土に持ち込まれると、砂糖が用いられるのが一般的になり、甘葛を用いる製法は廃れていきます。
「練り羊羹」が日本の歴史に登場するのは慶長4年(1599年)で、鶴屋(後に駿河屋と改名)の五代目、善右衛門がテングサ(寒天の原料)・粗糖・小豆あんを用いて炊き上げる煉羊羹を開発したものが広まってからです。(他説あり)
当初、水羊羹(みずようかん)は、御節料理の料理菓子として冬の時季に作られたとか。御節料理としては、全国的にその風習も忘れられ、冷蔵技術の普及と嗜好の変化から通年化の傾向により、現在は主に夏に冷やして食されることが多いですが、地域によっては「こたつ羊羹」などとも呼ばれて、冬の寒い時期にしかお目見えしない水羊羹もあります。おこたに入って食べる、採れたて新豆の「こたつ羊羹」も、また格別の味わいでしょうか。
流し箱タイプのほか、アルミ缶やプラスチックカップに入った製品が市販され、高級和菓子店では棹物として、竹筒に入った製品なども販売されています。
夏の和菓子の定番「水羊羹」。。夏菓子の醍醐味を存分に味わいたいならば、水羊羹に行きつくのでは…?滑らかな口解けと、ひんやりとした優しい喉ごしが身上です。小豆の風味をストレートに味わうシンプルな配合ですので、素材の良し悪しと煮詰め濃度が大切です
今回は、近所の山で若竹を調達して・・・。

カットもなかなかの重労働


準備OKです。

で、・・・・出来上がりが。。。
「竹筒水羊羹」

本コース「青梅」
この時期は、二十四節気では芒種、七十二候ではその末候を「梅の子(み)黄ばむ」。梅の実が黄色く色づくとの意味です。旧暦では、立春から数えて百二十七日目を入梅(今年は6/11)としていて、この時期に降る雨なので「梅雨」という名が付いたとも言われています。
梅雨時の茶会の定番菓子銘の「青梅」。東京都の北西部には「青梅(おうめ)市」が存在します。市内の天ヶ瀬(あまがせ)という所に「金剛寺」というお寺があり、中庭に、石柱に囲まれた梅の老木があります。「将門誓いの梅」と呼ばれ、これが「青梅」という地名の由来になった梅の木と云われます。地名の起こりは諸説ありますが、この「将門誓いの梅」説が多くの人々に知られています。承平年間、平将門がこの地を訪れた際、馬の鞭に使用していた梅の枝を自ら地に挿し、「我願い成就あらば栄ふべし。しからずば枯れよかし」と願をかけたところ、見事に梅の枝は根付きました。ところが、この梅の木は実をつけるのですが、夏を過ぎても青いまま熟さずに、また、地に落ちることもなく枝に残っていました。当時の人々はこれを不思議に思い、この地を青梅と呼ぶようになったと伝えられます。「将門誓いの梅」は老木ですが、現在でもいくつかの実をつけ、秋になっても青い実を枝に残しているのを見ることができるようです。
さて、「外郎(ういろう)」とは室町時代の中国の黒い丸薬「透頂香(とうちんこう)」の日本名。とても苦かったので、口直しとして米粉と黒糖を混ぜて作られた菓子が外郎菓子の始まりです。棹物として有名ですが、今回は生地を青緑色に着色し、梅入りの白餡を包んで青梅に成形します。姿形は正に青梅、甘酸っぱい梅餡で梅雨時期でも美味しいお茶タイムを如何でしょうか?
尖った部分とおへその両方を形づくって。。



 ふるさと創菓処 扇松堂
ふるさと創菓処 扇松堂
 住所
住所 電話・FAX
電話・FAX 営業時間
営業時間 定休日
定休日  駐車場
駐車場 アクセス
アクセス