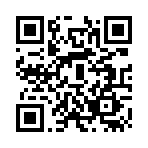2012年10月16日
はりはら塾「鹿の子」
10月のはりはら塾「いと、お菓子!」は文字通りの鹿の子三昧です。
小豆かのこ・栗かのこ・芋かのこ
ウィキぺディア(インターネット辞典)によれば、
≪鹿の子(かのこ)は、鹿の子餅とも呼ばれる。鹿の子は3から4層の構造になる。まず餅、求肥、羊羹のうちどれかを芯とし、そのまわりに餡をつける。できた餡玉に鹿の子豆と呼ばれる形の整った豆の蜜漬けを外側に隙間なくつけて完成する。最後につやを出すため寒天につけることもある。
鹿の子豆に使われる豆は小豆や金時豆、うづら豆やうぐいす豆などがある。鹿の子豆は硬めで形の整ったものであれば豆でなくてもよく、栗を使った栗鹿の子も一般的で、長野県小布施町などの名物となっている。また、白いんげんを鹿の子豆に使ったものは京鹿の子と呼れることがある。小豆の場合は小倉野という名でも呼ばれる。
鹿の子がはじめて作られたのは宝暦年間で、江戸の人形町にあったエビス屋という和菓子屋から売り出されたが、この店は嵐音八という役者の実家であり、役者手製の餅菓子として評判を呼び全国に広まったという。その後、芯に餅の代わりに求肥や羊羹を用いることも行われるようになった。≫
以上、「かのこ」は江戸時代にはすでにあった上菓子で、現在も人気が高く喜ばれます。「鹿の子」と書くように、整った粒が隙間なく並ぶさまが鹿の背の斑点を思わせ、小鹿の背にあるまだら模様に似ているところからの由来だとされています。製法も求肥を芯に餡を丸め、小豆や青えんどう、金時豆、栗などを甘く軟らかく煮たものを周りに付けただけで手軽に作れるものです。
栗かのこは、豪華で見栄えもすることから、正月やお祝いにも使われます。
芋かのこは、細かくしたさつまいもを即席に甘茹でして、こちらは簡単おやつにおススメです。
仕上げは艶出し寒天、略して「つや天」で、これを使えばお菓子の見栄えが格段に上がって、見た目の美味しさもアップします。

小豆かのこ・栗かのこ・芋かのこ
ウィキぺディア(インターネット辞典)によれば、
≪鹿の子(かのこ)は、鹿の子餅とも呼ばれる。鹿の子は3から4層の構造になる。まず餅、求肥、羊羹のうちどれかを芯とし、そのまわりに餡をつける。できた餡玉に鹿の子豆と呼ばれる形の整った豆の蜜漬けを外側に隙間なくつけて完成する。最後につやを出すため寒天につけることもある。
鹿の子豆に使われる豆は小豆や金時豆、うづら豆やうぐいす豆などがある。鹿の子豆は硬めで形の整ったものであれば豆でなくてもよく、栗を使った栗鹿の子も一般的で、長野県小布施町などの名物となっている。また、白いんげんを鹿の子豆に使ったものは京鹿の子と呼れることがある。小豆の場合は小倉野という名でも呼ばれる。
鹿の子がはじめて作られたのは宝暦年間で、江戸の人形町にあったエビス屋という和菓子屋から売り出されたが、この店は嵐音八という役者の実家であり、役者手製の餅菓子として評判を呼び全国に広まったという。その後、芯に餅の代わりに求肥や羊羹を用いることも行われるようになった。≫
以上、「かのこ」は江戸時代にはすでにあった上菓子で、現在も人気が高く喜ばれます。「鹿の子」と書くように、整った粒が隙間なく並ぶさまが鹿の背の斑点を思わせ、小鹿の背にあるまだら模様に似ているところからの由来だとされています。製法も求肥を芯に餡を丸め、小豆や青えんどう、金時豆、栗などを甘く軟らかく煮たものを周りに付けただけで手軽に作れるものです。
栗かのこは、豪華で見栄えもすることから、正月やお祝いにも使われます。
芋かのこは、細かくしたさつまいもを即席に甘茹でして、こちらは簡単おやつにおススメです。
仕上げは艶出し寒天、略して「つや天」で、これを使えばお菓子の見栄えが格段に上がって、見た目の美味しさもアップします。

Posted by 扇松DO at 00:00│Comments(0)
│いと、お菓子!






 ふるさと創菓処 扇松堂
ふるさと創菓処 扇松堂
 住所
住所 電話・FAX
電話・FAX 営業時間
営業時間 定休日
定休日  駐車場
駐車場 アクセス
アクセス