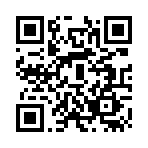2018年06月27日
土木LOVE DOBOCLUB どぼどら
静岡県を守るんだ~♪
静岡県の「土木」を応援します。。。
出来ました「どぼどら」

たっぷり蜂蜜とやぶきた茶入の2種類
採れたて新鮮卵と国産小麦、牧之原産深蒸しやぶきた煎茶を使用しています




紅白饅頭バージョンも・・・

ご注文のみでお作りします
静岡どぼくらぶ
https://www.pref.shizuoka.jp/.../howtousedoboclubsong.html
静岡県の「土木」を応援します。。。
出来ました「どぼどら」

たっぷり蜂蜜とやぶきた茶入の2種類
採れたて新鮮卵と国産小麦、牧之原産深蒸しやぶきた煎茶を使用しています




紅白饅頭バージョンも・・・

ご注文のみでお作りします
静岡どぼくらぶ
https://www.pref.shizuoka.jp/.../howtousedoboclubsong.html
タグ :静岡どぼくらぶ
2018年06月27日
いと、お菓子!2018 6月
ご案内
「芒種」。芒(のぎ)とは、稲などの穂の先についているトゲのようなもののこと。早苗を苗代から田に移す、田植えの季節です。先人は、ホタルは腐った落ち葉が変身したと想像し、「腐れたる草螢と為る」と表しています。夏の虫たちが出揃うと、梅雨の到来です。立春から百二十七日目を「梅雨入り」、梅の子が黄ばむ時期に降る雨だから「梅雨」といわれます。
はりはら塾
ババロア・オ・フリュイ
初夏、汗ばむ季節になると美味しいのが、冷やして食べる冷たいスイーツ。ババロアは、スプーンですくって口に入れた瞬間に、幸せが体中に広がり、子どもから大人まで広く好まれます。この時期にプリンや果汁たっぷりのフルーツゼリー、泡のような口当たりのムースと並んでショーケースに登場します。語源はドイツ南部のババリア(バイエルン)地方に由来。この地方の温かい飲み物で、紅茶やアルコール、シロップ、牛乳などを混ぜ合わせて作ったものがルーツとか。。これをゼリーの考案者でもある19世紀初頭フランスの著名な菓子職人アントナン・カレームが冷たいお菓子に作り上げたと言われています。
ムースは、卵白や生クリームを泡立てた中にチョコレートやフルーツピュレなどを加えて風味をつけ、卵黄などをつなぎにして冷やし、軽くふんわりと仕上げたお菓子。ババロアは、卵、牛乳、砂糖、泡立てた生クリームなどをゼラチンで固めたお菓子。ムースとババロアの違いは、ムースは泡立てた素材を自然に固めたものであるのに対し、ババロアはゼラチンを使っている点です。ムースの方がふんわりと軽い食感があります。
「ババロア・バニーユ」は、洋菓子の世界では基本のソースのひとつ「アングレーズ」をベースにしたデザート。アングレーズソースとは、牛乳、卵、砂糖を弱火でじっくりと炊き上げて作ったソースで、濃厚な素材の味わいが楽しめるソースです。バニラの香りも贅沢に使ってリッチな味わいを楽しめます。
基本の配合をマスターできたら、チョコレート等を加えたりして、いろいろなバリエーションも楽しめます。涼しげなカップに冷やし固めたババロアを、クレーム・シャンティ、フルーツ等を色とりどりに飾って、見た目にも華やかなデザートに仕上げてみましょう。

はりはら塾
黒蜜黄な粉プリン
老若男女誰からも好かれ、子ども時代の思い出の黄金の味「プリン」。本来は「プディング(pudding)」意味は「腫れもの」。その始まりは、イギリス人の「もったいない精神」だったといわれています。パンくずを捨てるのがもったいないと思った主婦が、小麦粉・レーズン・卵などのあり合わせの材料を混ぜ合わせ、塩とスパイスで味付し、布巾で包んで蒸し煮したのが始まりで、その後、大航海時代にはまかないメニュ-として船上でも少ない食材を工夫して「プリン」は作られたそうです。
日本でお馴染みの「カスタードプリン」はフランス生まれで、フランス語では「クリーム・ランヴェルセ(クリームをひっくり返した)」と呼ばれ、出来上がったものを逆さにしてお皿に盛りつけるところからの名前です。卵・砂糖・牛乳を合わせて蒸し焼きにします。現在では、ゼラチンなどの凝固剤を使用したものもあります
定番のカスタードプリンに生クリームやフルーツをトッピングしたデザートを「プリン・ア・ラ・モード」。こちらの発祥は、横浜の老舗ホテル「ホテル・ニューグランド」です。
プリンに欠かせないのが「カラメル」砂糖を煮詰めて焦がしたもの。プリンが日本に伝わったのが幕末の頃といわれていますが、カラメルは室町末期にポルトガルから「カルメイラ」として伝来しています。縁日でお馴染みの「カルメ焼き」として今日でも見かけます。
イギリスの諺に、「プリンは食べてみなければわからない」、日本では「論より証拠」と同じ。多くの種類のプリンがありますが、実際に食べてみないと・・・(o^^o)。

県営吉田公園緑花大学
お題「芒種」

青梅・薔薇・紫陽花 練りきり製
「芒種」。芒(のぎ)とは、稲などの穂の先についているトゲのようなもののこと。早苗を苗代から田に移す、田植えの季節です。先人は、ホタルは腐った落ち葉が変身したと想像し、「腐れたる草螢と為る」と表しています。夏の虫たちが出揃うと、梅雨の到来です。立春から百二十七日目を「梅雨入り」、梅の子が黄ばむ時期に降る雨だから「梅雨」といわれます。
はりはら塾
ババロア・オ・フリュイ
初夏、汗ばむ季節になると美味しいのが、冷やして食べる冷たいスイーツ。ババロアは、スプーンですくって口に入れた瞬間に、幸せが体中に広がり、子どもから大人まで広く好まれます。この時期にプリンや果汁たっぷりのフルーツゼリー、泡のような口当たりのムースと並んでショーケースに登場します。語源はドイツ南部のババリア(バイエルン)地方に由来。この地方の温かい飲み物で、紅茶やアルコール、シロップ、牛乳などを混ぜ合わせて作ったものがルーツとか。。これをゼリーの考案者でもある19世紀初頭フランスの著名な菓子職人アントナン・カレームが冷たいお菓子に作り上げたと言われています。
ムースは、卵白や生クリームを泡立てた中にチョコレートやフルーツピュレなどを加えて風味をつけ、卵黄などをつなぎにして冷やし、軽くふんわりと仕上げたお菓子。ババロアは、卵、牛乳、砂糖、泡立てた生クリームなどをゼラチンで固めたお菓子。ムースとババロアの違いは、ムースは泡立てた素材を自然に固めたものであるのに対し、ババロアはゼラチンを使っている点です。ムースの方がふんわりと軽い食感があります。
「ババロア・バニーユ」は、洋菓子の世界では基本のソースのひとつ「アングレーズ」をベースにしたデザート。アングレーズソースとは、牛乳、卵、砂糖を弱火でじっくりと炊き上げて作ったソースで、濃厚な素材の味わいが楽しめるソースです。バニラの香りも贅沢に使ってリッチな味わいを楽しめます。
基本の配合をマスターできたら、チョコレート等を加えたりして、いろいろなバリエーションも楽しめます。涼しげなカップに冷やし固めたババロアを、クレーム・シャンティ、フルーツ等を色とりどりに飾って、見た目にも華やかなデザートに仕上げてみましょう。

はりはら塾
黒蜜黄な粉プリン
老若男女誰からも好かれ、子ども時代の思い出の黄金の味「プリン」。本来は「プディング(pudding)」意味は「腫れもの」。その始まりは、イギリス人の「もったいない精神」だったといわれています。パンくずを捨てるのがもったいないと思った主婦が、小麦粉・レーズン・卵などのあり合わせの材料を混ぜ合わせ、塩とスパイスで味付し、布巾で包んで蒸し煮したのが始まりで、その後、大航海時代にはまかないメニュ-として船上でも少ない食材を工夫して「プリン」は作られたそうです。
日本でお馴染みの「カスタードプリン」はフランス生まれで、フランス語では「クリーム・ランヴェルセ(クリームをひっくり返した)」と呼ばれ、出来上がったものを逆さにしてお皿に盛りつけるところからの名前です。卵・砂糖・牛乳を合わせて蒸し焼きにします。現在では、ゼラチンなどの凝固剤を使用したものもあります
定番のカスタードプリンに生クリームやフルーツをトッピングしたデザートを「プリン・ア・ラ・モード」。こちらの発祥は、横浜の老舗ホテル「ホテル・ニューグランド」です。
プリンに欠かせないのが「カラメル」砂糖を煮詰めて焦がしたもの。プリンが日本に伝わったのが幕末の頃といわれていますが、カラメルは室町末期にポルトガルから「カルメイラ」として伝来しています。縁日でお馴染みの「カルメ焼き」として今日でも見かけます。
イギリスの諺に、「プリンは食べてみなければわからない」、日本では「論より証拠」と同じ。多くの種類のプリンがありますが、実際に食べてみないと・・・(o^^o)。

県営吉田公園緑花大学
お題「芒種」

青梅・薔薇・紫陽花 練りきり製
2018年06月27日
いと、お菓子!2018 5月
ご案内
春雨が止み、きらきら光る雨粒が夏の到来を告げます。気温はさほどに高くはありませんが、陽の光は一年中で最も強く、「光の夏」とも言われます。この強い日差しをうけ、草木の葉が青々と茂り、緑を濃く湛えている様を「万緑」、そんな草木の精気を吹き送る風が「薫風」です。風薫る初夏、何もかもが生き生きとして眩しい季節です。蛙が始めて鳴き、蚯蚓出で、笋生ず。夏が立ちました。
はりはら塾
「かしわ餅」
餅菓子は、糯(もちごめ)を原料にして搗いたいわゆる「餅(もち)」ではなく、中国で呼ばれる「餅(ぺい)」のことで、古書「嬉遊笑覧」に《餅は粉をつくねて蒸しただんご》とあるように、米粉・小麦粉・白玉粉・道明寺粉などの各種粉末原料を工夫して作られたものです。有名な「月餅」などは焼き饅頭ですが、これも餅菓子???、、、、。。
柏の葉は、古代では食器として使用されてたそうな・・・。また、新葉が出るまで散らないことから、無病息災と子孫繁栄の縁起物として、端午の節句(旧暦では6月初旬)には欠かせません。この「端午の節句」、そもそもは女性の特別な日だったそうです。5月は田植えの季節。田植えは女性の仕事で、「早乙女」は菖蒲やよもぎを軒先につるした家の中で一夜籠もりをして身を清める「五月忌み」の習慣がありました。現在は男の子の節句として定着していますが、これは江戸時代に五節句の一つに定められてからです。
ツバメが飛来して、田植えが終わればもうすぐ初夏。和菓子を代表するひとつ「かしわ餅」の季節です。米と小豆と柏の葉。日本の自然の恵みに感謝して健やかな生活を送りたいものですね。

吉田公園緑花大学
お題「立夏」

若葉・花菖蒲 練りきり製
春雨が止み、きらきら光る雨粒が夏の到来を告げます。気温はさほどに高くはありませんが、陽の光は一年中で最も強く、「光の夏」とも言われます。この強い日差しをうけ、草木の葉が青々と茂り、緑を濃く湛えている様を「万緑」、そんな草木の精気を吹き送る風が「薫風」です。風薫る初夏、何もかもが生き生きとして眩しい季節です。蛙が始めて鳴き、蚯蚓出で、笋生ず。夏が立ちました。
はりはら塾
「かしわ餅」
餅菓子は、糯(もちごめ)を原料にして搗いたいわゆる「餅(もち)」ではなく、中国で呼ばれる「餅(ぺい)」のことで、古書「嬉遊笑覧」に《餅は粉をつくねて蒸しただんご》とあるように、米粉・小麦粉・白玉粉・道明寺粉などの各種粉末原料を工夫して作られたものです。有名な「月餅」などは焼き饅頭ですが、これも餅菓子???、、、、。。
柏の葉は、古代では食器として使用されてたそうな・・・。また、新葉が出るまで散らないことから、無病息災と子孫繁栄の縁起物として、端午の節句(旧暦では6月初旬)には欠かせません。この「端午の節句」、そもそもは女性の特別な日だったそうです。5月は田植えの季節。田植えは女性の仕事で、「早乙女」は菖蒲やよもぎを軒先につるした家の中で一夜籠もりをして身を清める「五月忌み」の習慣がありました。現在は男の子の節句として定着していますが、これは江戸時代に五節句の一つに定められてからです。
ツバメが飛来して、田植えが終わればもうすぐ初夏。和菓子を代表するひとつ「かしわ餅」の季節です。米と小豆と柏の葉。日本の自然の恵みに感謝して健やかな生活を送りたいものですね。

吉田公園緑花大学
お題「立夏」

若葉・花菖蒲 練りきり製
2018年06月27日
いと、お菓子!2018 4月
ご案内
「花七日」。桜の盛りを表す言葉です。「サクラ」と言えば、全国の桜の8割を占めるソメイヨシノですが、江戸時代以前は青い山間を白淡い桃色で彩るヤマザクラの事でした。里山で多くの生きものたちと共生し、人知れず子孫を増やしています。長い年月を、周りの木や生きものと同じ風土、同じ季節の流れの中で生きていくようです。
はりはら塾「いと、お菓子!」にご参加いただき有難う御座います。四季の移ろいやイベントを菓子で表現して、ゆっくりと流れる余暇を楽しむお手伝いが出来れば幸いです。宜しくお願いいたします。
はりはら塾
「桜とやぶきた茶の浮島ケーキ」
浮島生地は、上生菓子や朝生菓子として扱われる蒸し物です。卵、砂糖、粉類、餡で作った生地を蒸して作ります。上生菓子にする場合、羊羹などと流し合わせたり、焼印を押したりします。茶席菓子としても饗される「浮島」、名前からもふわふわ感が伝わってきます。餡を主体にした蒸し菓子なので、口どけもよく、卵の気泡で浮かせた生地は香りも豊かです。切り分けて頂く「棹菓子」にも用いられる代表的な生地で、きめ細かく、軟らかすぎず固すぎず、ほろりと口の中で溶ける生地の微妙な質感が美味しさの決め手です。
甘露煮の栗やかのこ豆との相性も良く、生地に混ぜ入れたり、表面に散らして趣を凝らします。また、着色で季節を彩ったり、味の違う同生地を流し合わせて組み合わせを愉しむことも出来ます。
年間を通して作られますが、夏場は冷蔵庫で冷やしても美味しくいただけます。

県営吉田公園 緑花大学
お題「卯月」

桜花・サクラ 練りきり製
「花七日」。桜の盛りを表す言葉です。「サクラ」と言えば、全国の桜の8割を占めるソメイヨシノですが、江戸時代以前は青い山間を白淡い桃色で彩るヤマザクラの事でした。里山で多くの生きものたちと共生し、人知れず子孫を増やしています。長い年月を、周りの木や生きものと同じ風土、同じ季節の流れの中で生きていくようです。
はりはら塾「いと、お菓子!」にご参加いただき有難う御座います。四季の移ろいやイベントを菓子で表現して、ゆっくりと流れる余暇を楽しむお手伝いが出来れば幸いです。宜しくお願いいたします。
はりはら塾
「桜とやぶきた茶の浮島ケーキ」
浮島生地は、上生菓子や朝生菓子として扱われる蒸し物です。卵、砂糖、粉類、餡で作った生地を蒸して作ります。上生菓子にする場合、羊羹などと流し合わせたり、焼印を押したりします。茶席菓子としても饗される「浮島」、名前からもふわふわ感が伝わってきます。餡を主体にした蒸し菓子なので、口どけもよく、卵の気泡で浮かせた生地は香りも豊かです。切り分けて頂く「棹菓子」にも用いられる代表的な生地で、きめ細かく、軟らかすぎず固すぎず、ほろりと口の中で溶ける生地の微妙な質感が美味しさの決め手です。
甘露煮の栗やかのこ豆との相性も良く、生地に混ぜ入れたり、表面に散らして趣を凝らします。また、着色で季節を彩ったり、味の違う同生地を流し合わせて組み合わせを愉しむことも出来ます。
年間を通して作られますが、夏場は冷蔵庫で冷やしても美味しくいただけます。

県営吉田公園 緑花大学
お題「卯月」

桜花・サクラ 練りきり製


 ふるさと創菓処 扇松堂
ふるさと創菓処 扇松堂
 住所
住所 電話・FAX
電話・FAX 営業時間
営業時間 定休日
定休日  駐車場
駐車場 アクセス
アクセス