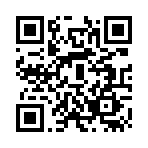2012年10月13日
新米大福餅
新米の季節
もち米も新米入荷です。
24年産 もち米 羽二重 無洗米です。

羽二重はお米の品種名

名前の通り、色が白くキメの細かい上品なお餅に仕上がります。
生産者はご家族皆さん顔馴染みのご近所、山本耕業さん
扇松堂のお餅やお赤飯は、お客様がもち米持参の場合を除いて、すべて羽二重を使用しています。
丁寧なお米作りで美味しいお米をいただいています。大満足です。
蒸して、臼に移して

杵で搗きあげて

北海道小豆の皮ムキ餡を包んで大福餅に

そろそろ温かいお茶とヤワヤワの新米大福餅でおやつの時間が愛おしい季節じゃないでしょうか?

もち米も新米入荷です。
24年産 もち米 羽二重 無洗米です。

羽二重はお米の品種名

名前の通り、色が白くキメの細かい上品なお餅に仕上がります。
生産者はご家族皆さん顔馴染みのご近所、山本耕業さん
扇松堂のお餅やお赤飯は、お客様がもち米持参の場合を除いて、すべて羽二重を使用しています。
丁寧なお米作りで美味しいお米をいただいています。大満足です。

蒸して、臼に移して

杵で搗きあげて

北海道小豆の皮ムキ餡を包んで大福餅に

そろそろ温かいお茶とヤワヤワの新米大福餅でおやつの時間が愛おしい季節じゃないでしょうか?

2012年10月13日
榛原ふるさとの森をお散歩
牧之原市内、切山の「榛原ふるさとの森」をお散歩。。
この季節、なかなか爽やかに山歩きが楽しめます。
不思議発見や楽しいびっくりが其処らじゅうにころがっています。
時折、飛来するスズメバチや枯れ葉の中を音も無く去っていくマムシなどに注意すれば 、遊歩道も整備されていてお薦めのお散歩コース
、遊歩道も整備されていてお薦めのお散歩コース
秋の里山の味覚の代表格
栗


早速茹でて・・・、
小指の爪ほどのちっちゃな栗もかなりの美味しさです。
ただし、食べるのが面倒くさい

他にも・・・・・・。

ホトトギス・・・・・・鳥のホトトギスの胸の模様にそっくりの花

たぶんノササゲ、これからサヤが綺麗な紫色に変化します。

イヌホオズキ

スズメウリ・・・オレンジ色のカラスウリは有名ですが、こちらは名前の通り小さくて可愛い。
未成熟な実はキュウリの味がして美味しいとか。。。。

山芋のむかご。。。炊き込みご飯やおつまみに

ツリガネニンジン・・・・可愛い釣鐘型の薄紫の花がぶらさがります。根っこがニンジンに似ているんだとか。。。
お時間があれば里山散歩いかがでしょう

この季節、なかなか爽やかに山歩きが楽しめます。
不思議発見や楽しいびっくりが其処らじゅうにころがっています。
時折、飛来するスズメバチや枯れ葉の中を音も無く去っていくマムシなどに注意すれば
 、遊歩道も整備されていてお薦めのお散歩コース
、遊歩道も整備されていてお薦めのお散歩コース秋の里山の味覚の代表格
栗


早速茹でて・・・、
小指の爪ほどのちっちゃな栗もかなりの美味しさです。
ただし、食べるのが面倒くさい

他にも・・・・・・。

ホトトギス・・・・・・鳥のホトトギスの胸の模様にそっくりの花

たぶんノササゲ、これからサヤが綺麗な紫色に変化します。

イヌホオズキ

スズメウリ・・・オレンジ色のカラスウリは有名ですが、こちらは名前の通り小さくて可愛い。
未成熟な実はキュウリの味がして美味しいとか。。。。

山芋のむかご。。。炊き込みご飯やおつまみに


ツリガネニンジン・・・・可愛い釣鐘型の薄紫の花がぶらさがります。根っこがニンジンに似ているんだとか。。。
お時間があれば里山散歩いかがでしょう

2012年10月13日
はりはら塾「くるみ餅」
10月のはりはら塾 いと、お菓子!小習いコース
「くるみ餅」 外郎製、小豆漉し餡入り

「外郎」(ういろう)は人の名前で、鎌倉時代の中国の礼法官。「唐頂香」(とうちんこう)という名薬を日本に伝え、その口直しとして黒糖と米粉などで蒸し菓子を作り、これが「外郎」と呼ばれ、そのまま菓子の名前となったのが由来です。後に外郎氏の子孫達が薬学によって各地の大名に招かれた折に、その土地の菓子司に製法を伝授し、各地の風土や職人の工夫で少しづつ変化して、現在も京都、小田原、名古屋、山口、宮崎などでは名産として続いています。
今回の「くるみ餅」は、それを餅生地としてクルミを混ぜ込んで、香ばしい味に仕上げ、漉し餡を包みます。クルミの他に醤油や梅肉を入れたりしても楽しめます。

包餡もなかなかの腕前に・・・。
慣れれば、それほど苦にならないと感じます。
時間内で作業も終わり、皆さんのご協力と上達に感謝です。
お疲れさまでした。
「くるみ餅」 外郎製、小豆漉し餡入り

「外郎」(ういろう)は人の名前で、鎌倉時代の中国の礼法官。「唐頂香」(とうちんこう)という名薬を日本に伝え、その口直しとして黒糖と米粉などで蒸し菓子を作り、これが「外郎」と呼ばれ、そのまま菓子の名前となったのが由来です。後に外郎氏の子孫達が薬学によって各地の大名に招かれた折に、その土地の菓子司に製法を伝授し、各地の風土や職人の工夫で少しづつ変化して、現在も京都、小田原、名古屋、山口、宮崎などでは名産として続いています。
今回の「くるみ餅」は、それを餅生地としてクルミを混ぜ込んで、香ばしい味に仕上げ、漉し餡を包みます。クルミの他に醤油や梅肉を入れたりしても楽しめます。

包餡もなかなかの腕前に・・・。
慣れれば、それほど苦にならないと感じます。

時間内で作業も終わり、皆さんのご協力と上達に感謝です。
お疲れさまでした。


 ふるさと創菓処 扇松堂
ふるさと創菓処 扇松堂
 住所
住所 電話・FAX
電話・FAX 営業時間
営業時間 定休日
定休日  駐車場
駐車場 アクセス
アクセス